シニア犬の下痢は要注意!原因・対処法・食事のポイントを犬の管理栄養士が解説

シニア犬と暮らしていると、ちょっとした体調の変化にも敏感になりますよね。
なかでも毎日のうんちの状態は、不調をいち早く知らせてくれる大切なサインです。
高齢になると下痢をしやすくなり、「元気も食欲もあるのに、どうして?」と悩んでしまうこともあるでしょう。
さらに、下痢が続いたり嘔吐を伴ったりすると、「何かの病気かもしれない」と心配になるママさん、パパさんも多いはずです。
そこで今回は、シニア犬の下痢について、主な原因や動物病院を受診すべきタイミング、そして気になる食事のポイントを犬の管理栄養士が解説します。
老犬が下痢をしやすいのは、腸内環境が悪化しているから

私たち人間と同じように、シニア期に入った愛犬は、加齢によって体の様々な機能が少しずつ低下していきます。
その中のひとつが、腸内環境の悪化です。腸内で栄養を吸収するための器官である絨毛が萎縮していくため、栄養の吸収効率が落ち、善玉菌が減って悪玉菌が増えやすくなる傾向があります。
そうすると、若い頃には問題にならなかった小さな刺激(冷え・ストレス・食事の変化など)でも、腸が過敏に反応して下痢を引き起こすことがあります。
また、シニア犬は回復力も弱まっているので、下痢が長引くと体調を大きく崩す危険があるため注意が必要です。命に関わる重大な病気が隠れているケースも少なくありません。
それでは、シニア犬の下痢に多い主な原因を確認していきましょう。
シニア犬の下痢で考えられる5つの原因
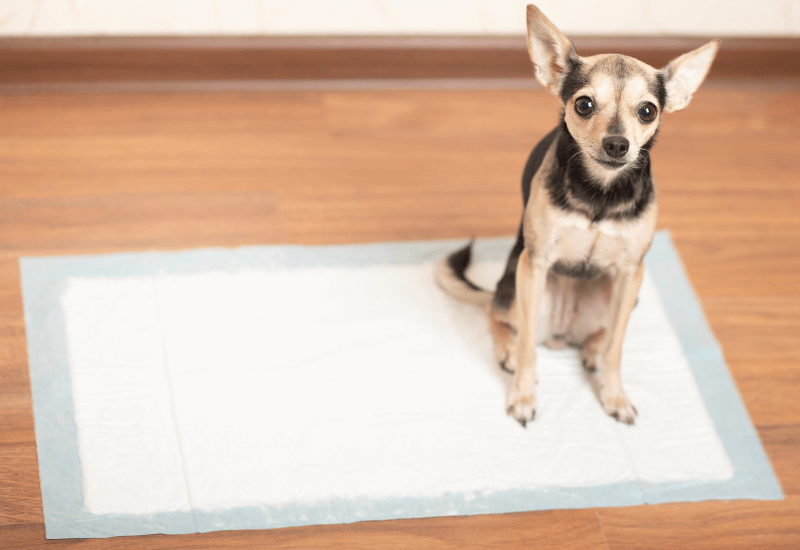
シニア期の愛犬が下痢をする原因として考えられるのは、主に次の5つです。
- ストレスや環境の変化、季節の変わり目
- フードの急な切り替えや食べ慣れないものを口にした
- 感染症や寄生虫
- 病気(腸・肝臓・腎臓・膵臓など)
- 薬の副作用や毒物
それぞれについて説明します。
①ストレスや環境の変化、季節の変わり目

犬は環境の変化に敏感です。引っ越し、飼い主の不在、家族構成の変化などはストレスとなり、自律神経の働きに影響を与えて下痢を引き起こすことがあります。
シニア犬は五感の衰えや感情の制御が難しくなってくいるので、特にストレスを抱えやすい状態です。
また、寒暖差や気圧の変化が大きい季節の変わり目は、腸の働きが乱れやすくなります。そのうえ、シニア犬は体温調節が苦手なので体が冷えやすい状態です。
私たちと同様に、冷えはお腹を壊す原因になります。
②フードの急な切り替えや食べ慣れないもの

ドッグフードを急に新しいものに切り替えたり、これまで食べたことがない物を突然与えたりすると、食べ慣れない物にお腹がびっくりしてしまい下痢をすることがあります。
これは若い犬でも同様なので、消化吸収能力が衰えているシニア期の愛犬であればなおさら注意が必要です。
③感染症や寄生虫

細菌やウイルスによる感染症、寄生虫も下痢の原因になります。シニア期の愛犬は免疫力が低下しているため、若い頃より感染症にかかりやすい傾向があります。
そのため、特別な理由がなければワクチン接種や寄生虫予防を欠かさず行い、半年に1回程度は健康診断を受けるようにしましょう。
④病気(肝臓・腎臓・膵臓など)

炎症性腸炎や膵炎、膵外分泌不全、胆泥症、腎臓病、副腎皮質機能低下症、腫瘍、子宮蓄膿症、食物アレルギー、熱中症などの病気が原因で下痢をしている可能性もあります。
命に関わる病気も多いため、早めに異変に気づき、適切な治療につなげることが大切です。
⑤薬の副作用や毒物

シニア期に入ると持病がある犬も多く、処方された抗生物質やステロイド、抗がん剤などが腸に影響して下痢を引き起こすことがあります。
また、若い犬よりは頻度は高くないとはいえ、散歩中に除草剤のついた草を誤って口にしてしまったり、落ちているものを食べたりといった、異物の誤飲にも注意が必要です。
シニア犬の下痢で動物病院を受診すべきタイミング

シニア期の愛犬が下痢をしたときは、1度は動物病院を受診しておくと安心です。
ですが、時間帯によってはすぐには連れていけないこともあるでしょう。また、元気や食欲があり、受診を迷ってしまうこともありますよね。
ここでは、シニア犬の下痢で動物病院を受診すべきタイミングの目安を紹介します。
すぐに受診すべき下痢
- 血便・黒色便が出ている
- 嘔吐や発熱を伴う
- 元気がなく、水も飲まない
- 食欲がない
- 短期間で急激に痩せている
ひとつでも当てはまるときは、命に関わる病気が潜んでいる可能性があるためすぐに動物病院へ行きましょう。
2日以上続くなら受診すべき下痢
- 泥のような下痢
- ティッシュでつかめないがやや形がある
- 元気・食欲があり、水もしっかり飲んでいる
上記はあくまでも目安です。シニア犬は体調が急変しやすいため、少しでも不安を感じたら早めに動物病院を受診しましょう。
シニア犬が下痢をしたときの対処法Q&A

シニア期の愛犬が下痢をしたときの対処法として、悩みがちなポイントにお答えします。
Q.下痢のときは絶食・絶水のほうがいい?

A.シニア期の愛犬は体力を消耗しやすいため、絶食はあまりおすすめできません。いつものフードを4分の1程度の量にしてふやかして与えるようにしましょう。
また、下痢は脱水を招きやすいため水分補給は必須です。いつでも新鮮な水を飲めるようにしておきましょう。
もし水を飲みたがらない場合は、ウェットフードや犬用のゼリー、スープなどを活用してみてください。
Q.サプリメントやビオフェルミンを与えてもいい?

A.腸内環境を整えるために、乳酸菌やオリゴ糖を含む犬用のサプリメントを利用するのも一つの方法です。
ただし、ビオフェルミンなどの人用整腸剤を安易に愛犬に与えるのは避けましょう。犬の体質や下痢の原因によっては、逆に腸内細菌叢を乱したり改善を遅らせたりすることがあります。
ビオフェルミンを与えたい場合は、犬専用の「わんビオフェルミン」がおすすめです。
また、サプリメントを使用する前に獣医師に相談し、適切な量・タイミングで使うようにしてください。
シニア犬の下痢を予防するためにできること

シニア犬の下痢を防ぐには、日頃のサポートが重要です。ここでは、食事管理・温度管理・ストレスケア・定期検診という4つのポイントに分けて解説します。
食事管理

ドッグフードはシニア専用の総合栄養食や、消化器の健康維持に配慮した栄養バランスのものを選ぶようにしましょう。
具体的には、低脂肪で繊維質を適度に配合しているものや、良質なタンパク質を使用しているもの、消化のしやすい加工をしているものなどです。
また、愛犬の体重や年齢にあった量を毎回軽量して与えるようにして食べ過ぎを防ぎましょう。
フードを切り替えるときは、1週間から10日程度かけて少しずつ移行すると、胃腸への負担も軽くなります。
おやつやトッピングも、脂肪や塩分が少なく、犬がもともと慣れている食材や消化の良いものに限定しましょう。ジャーキーや硬いおやつはあまりおすすめできません。
温度管理

夏場の暑さや冬場の冷えは下痢の原因になりうるため、シニア犬が過ごす場所の温度・湿度の管理は重要です。
室内の温度と湿度の目安は、
- 気温…25度前後
- 湿度…50%程度
なので、参考にしてください。
夏場はエアコンでの温度管理はもちろんのこと、愛犬が冷えすぎないようにベッドにタオルをひくなどの対策もしておきましょう。
また冬場は冷えにより腸の働きが鈍くなりやすいため、洋服・腹巻き・毛布・ペットヒーターなどで暖を取らせるようにします。
秋や春などの季節の変わり目は、室内との寒暖差が大きくなりすぎないように、散歩の時間を工夫しておくと安心です。
ストレスケア

急な環境の変化や大きな刺激をできるだけ避け、安心できる生活リズムを整えてあげることで、腸内環境が安定しやすくなります。
体調が悪かったり悪天候でない限りは、なるべく毎日散歩に行くようにしましょう。
長い距離を歩く必要はないので、シニア犬のペースで適度に運動をさせてください。
あまり歩けない愛犬の場合でも、カートに乗って外に出るだけでリフレッシュになります。
また、ママさん、パパさんとのスキンシップや愛犬のお気に入りの場所で静かに過ごせるような環境づくりも大切です。
定期的な健康診断

シニア期の愛犬は、半年に1回程度のスパンで健康診断を受けるようにして、血液検査や超音波検査で内臓の異常を早期にキャッチしましょう。
下痢以外にも元気消失・体重減少・嘔吐・血便などが見られたら、早めに受診することが重要です。
病気に気がつくきっかけは「なんとなくフードの食いつきが悪いな」という程度であることも珍しくありません。異変を感じたら、獣医師に相談・必要な検査をしておくと安心です。
まとめ

シニア期は加齢による腸内環境の低下により、若い頃に比べて下痢をしやすく、また重症化しやすい傾向があります。
原因もフードの切り替えや環境の変化といった身近なものから、感染症や内臓疾患など命に関わる病気までさまざまです。
「しばらくすれば治るだろう」と放置せず、少しでも異変を感じたら早めに動物病院を受診するようにしましょう。
また、日頃から消化に配慮した食事選び、規則正しい生活リズム、温度管理やストレスケア、定期健診といった基本的なサポートを続けていくこと、下痢の予防につながります。
愛犬が健やかにシニア期を過ごせるように、一緒にサポートしていきましょう!

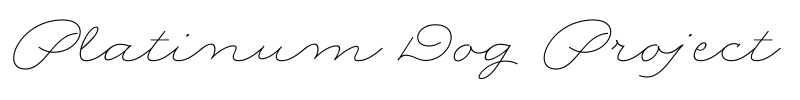

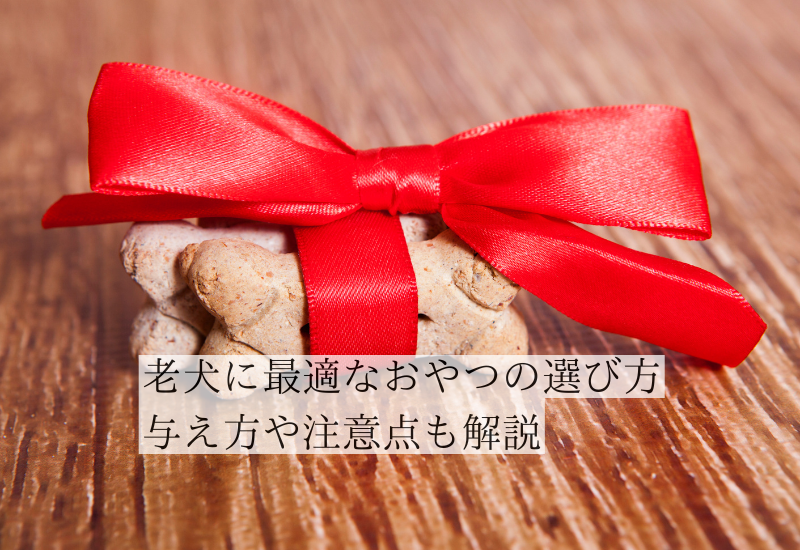










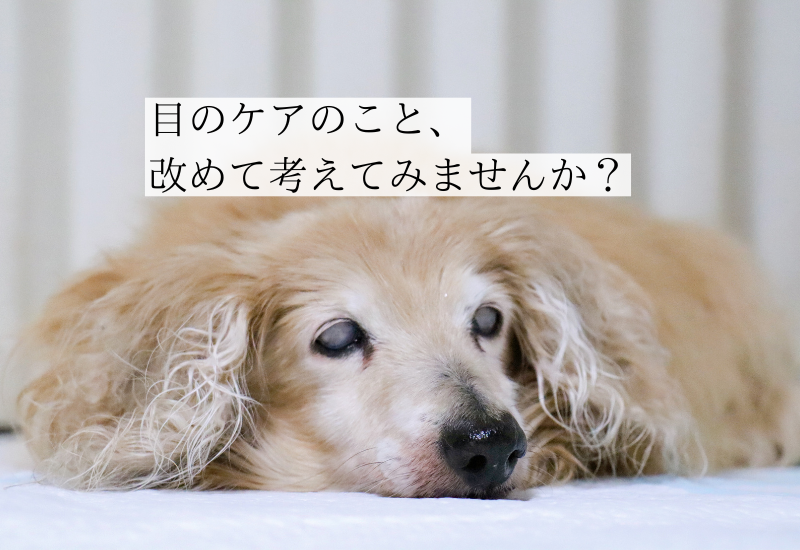
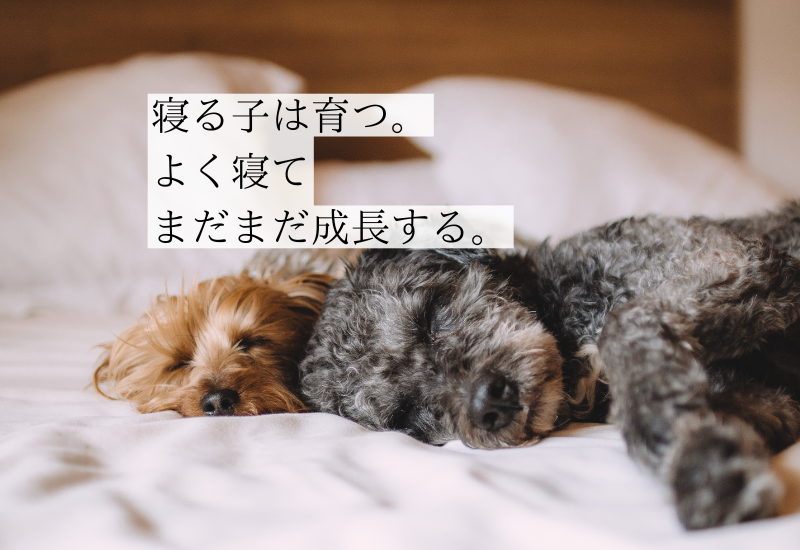
のシャンプーはどうする?頻度ややり方、注意点を解説-500x500.png)







この記事へのコメントはありません。