シニア犬の夜鳴きに困ったら?原因と対策、飼い主ができる工夫を徹底解説

「うちの子、夜鳴きがひどくて眠れない……」
そんな悩みを抱えるママさん、パパさんは多いのではないでしょうか。とくにシニア期に入った犬は、日中は穏やかに過ごしていても、夜になると急に不安そうに鳴き続けることがありますね。
シニア犬の夜鳴きは、飼い主にとって心身ともに大きな負担になりますが、決して珍しいことではありません。
加齢にともなう体や心の変化が背景にある場合が多く、原因を知ることが大切です。
この記事では、シニア犬と暮らしていた私が夜鳴きをする主な原因と、飼い主ができる対策について分かりやすく解説していきます。
シニア犬が夜鳴きをする主な原因5つ

シニア犬の夜鳴きにはいくつかの代表的な原因があります。複数が重なっている場合も多いため、ひとつずつ見ていきましょう。
1.認知症(犬の認知機能不全症候群)

シニア犬に多いのが、いわゆる「犬の認知症」です。昼夜が逆転し、夜になると活動的になって鳴き続けたり、理由もなく吠えたりすることがあります。
また、不安感や混乱から、飼い主を探すように鳴き続けるケースも少なくありません。
2.不安や寂しさ

聴力や視力が低下すると、犬は周囲の変化に敏感になり、不安から鳴くことがあります。特に夜は静かで暗いため、不安が増幅されやすい時間帯です。
ママさん、パパさんが寝室に行ってしまい、姿が見えなくなると不安で鳴いてしまう犬もいます。
とくに甘えん坊な性格の犬や、シニア期に入って感覚が鈍くなった犬は、少しの環境変化でも強い不安を感じやすくなります。
3. 身体的な不調や病気

夜間に痛みや不快感を感じて鳴いてしまう場合もあります。関節炎や内臓の不調、排泄トラブルなどが原因になることも珍しくありません。
シニア犬は病気が隠れていることも多いため、夜鳴きが続く場合は病院でのチェックが大切です。
4. 前庭疾患

シニア犬に比較的多い病気のひとつに「前庭疾患」があります。突然のふらつきや斜頸(首が傾く症状)、ぐるぐる同じ方向に回る行動が特徴です。
症状が出ている犬は強い不安や吐き気を感じやすく、夜間に落ち着かず鳴いてしまうことがあります。
回復するケースもありますが、認知症と似た夜鳴きが長引くこともあり、見極めには獣医師の診断が欠かせません。
5. 環境要因

部屋が暗すぎる、外の物音が気になる、気温が合わないなど、環境が原因で夜鳴きすることもあります。
シニア犬は感覚が敏感になったり逆に鈍くなったりするため、ちょっとした違和感が大きなストレスになるのです。
シニア犬の夜鳴きに困ったときの対策5つ

シニア犬の夜鳴きに悩むとき、まず大切なのは「原因を探りつつ、できることから試していく」ことです。
完全に止めるのは難しい場合もありますが、工夫次第で愛犬も飼い主もぐっと楽に過ごせるようになります。
そこでここからは、実際に試しやすい5つの対策をご紹介します。
1. 環境を安心できる空間に整える
.png)
犬が安心して眠れる場所をつくることは、夜鳴き対策の基本です。
- 飼い主の気配を感じられる場所にベッドを置く
- ほんのり明かりをつけて真っ暗にしない
- 外の音が気にならないように遮音カーテンを使う
こうしたちょっとした工夫で、不安からくる夜鳴きが和らぐケースは多く見られます。
特に高齢になると視覚や聴覚が衰えるため、わずかな暗がりや物音も不安を強めてしまうのです。
2. 日中にしっかり活動させる

無理のない範囲で散歩や遊びを取り入れ、適度に体を動かしましょう。
シニア犬は活動量が減りやすく、日中に十分な疲労感を得られないまま夜を迎えることが夜鳴きにつながることもあります。
ただし、長時間の運動は関節や心臓に負担になるため、短い散歩を数回に分けるなど調整が必要です。
さらに、足腰が弱ってきた犬には、歩行器や犬用車いすを取り入れてもいいでしょう。
サポートを受けながら歩くことで自力での移動が可能になり、運動不足の解消や気分転換になります。
こうした工夫で日中を過ごせれば、夜もぐっすり眠りやすくなるでしょう。
3. スキンシップで安心感を与える

夜鳴きが始まったとき、軽く撫でてあげるだけで安心して落ち着くことがあります。
シニア犬は「ママさん、パパさんと一緒にいる」こと自体が大きな安心材料です。ただし、毎回すぐに抱き上げたりすると「鳴けば来てくれる」と学習してしまい、逆に夜鳴きが習慣化することもあるので注意しましょう。
過度に反応せず、安心できる環境づくりとバランスを取ることが大切です。
4. 食事と排泄のリズムを整える

夜鳴きの背景に、排泄トラブルや空腹が隠れている場合もあります。
夕方以降の食事量や水分摂取量を調整し、寝る前に排泄を済ませる習慣をつけると、夜間の不快感を減らすことができます。
また、腎臓や膀胱のトラブルがある犬は夜間にトイレに行きたくなりやすいため、寝床のそばにペットシーツや室内トイレを設置しておくのも有効です。
5. 獣医師に相談する
.png)
夜鳴きが続く場合、単なる習慣ではなく病気のサインである可能性もあります。
認知症や前庭疾患、痛みを伴う病気などは家庭での工夫だけでは解決が難しいため、早めに獣医師に相談しましょう。
診察の結果によっては、サプリメントや漢方などの自然なケア、または必要に応じて睡眠をサポートするお薬が提案されることもあります。
投薬と聞くと少しハードルを感じるママさん、パパさんもいますが、「苦しさを和らげ、少しでも穏やかに眠れるようにするための手段」と考えると受け入れやすいかもしれません。
獣医師と相談しながら、その子に合った方法を選んでいきましょう。
夜鳴きが続く、日中も落ち着かない、食欲や歩行に変化が見られるなどこうしたときは自己判断せず、早めに獣医師に相談することが大切です。
相談の目安やタイミングについては、以下の記事で詳しくご紹介します。
シニア犬の夜鳴きに悩む家族の心構え

シニア犬の夜鳴きは、原因を探って工夫しても、すぐに解決するとは限りません。ときには「昨日は落ち着いていたのに、今日はまた鳴いている」という日が続くこともあります。
そんなとき、最も大切なのは一緒に過ごす家族が疲れ果てないことです。
1. 完璧を目指さない

夜鳴きが続くと、「なんとかして止めなければ」と強く思いがちです。
しかし、シニア犬にとって夜鳴きは自然な行動の一部であり、完全にゼロにするのは難しいケースも多いです。
まずは「少しでも和らげられればいい」と、ハードルを下げて向き合うことが大切です。
2. 家族の休養も優先する

シニア犬が夜鳴きをしていると、つい夜通し付き合ってしまうご家族もいますが、自分が心身ともに疲れてしまっては、長期的にお世話を続けられません。
耳栓やホワイトノイズを使う、別室で寝るなど、自分が休める環境を整えることも必要です。
また、家族がいれば交代で夜を担当するなど、負担を分け合えるなどの工夫をしましょう。
3. 小さな変化を喜ぶ

夜鳴きが続いていると、ママさん、パパさんは「改善が見られない」と落ち込みがちです。
しかし、昨日よりも少し落ち着いて眠れた、短い時間でも静かに過ごせたなど、小さな変化を見つけて喜ぶことも大切です。
シニア犬にとっても家族の明るい表情は安心材料になります。
4. 周囲の理解を得る

夜鳴きは家族だけでなく、近隣にも影響が及ぶ場合があります。
特にマンションや密集した住宅地では、夜中の鳴き声がご近所トラブルに発展することもあるため、注意が必要です。
可能であれば事情を説明して理解を得ておくと、精神的な負担が軽くなります。
また、同じ経験をしているママさん、パパさん同士のコミュニティやSNSでの交流も心の支えになるでしょう。
まとめ

シニア犬の夜鳴きには、認知症や不安、病気、環境の変化などさまざまな原因が隠れています。
すぐに解決することは難しいかもしれませんが、環境を整え、日中の活動を工夫し、必要に応じて獣医師に相談することで、少しずつ落ち着きを取り戻すことは可能です。
そして何より大切なのは、一緒に過ごすご家族自身が無理をしすぎないこと。
夜鳴きはシニア犬からの「今の私をわかってほしい」というサインでもあります。
その声を受け止めながら、できる範囲で寄り添っていく。それがシニア犬との暮らしを豊かにする第一歩になるでしょう。

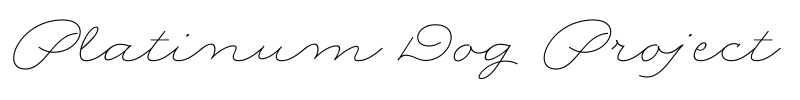
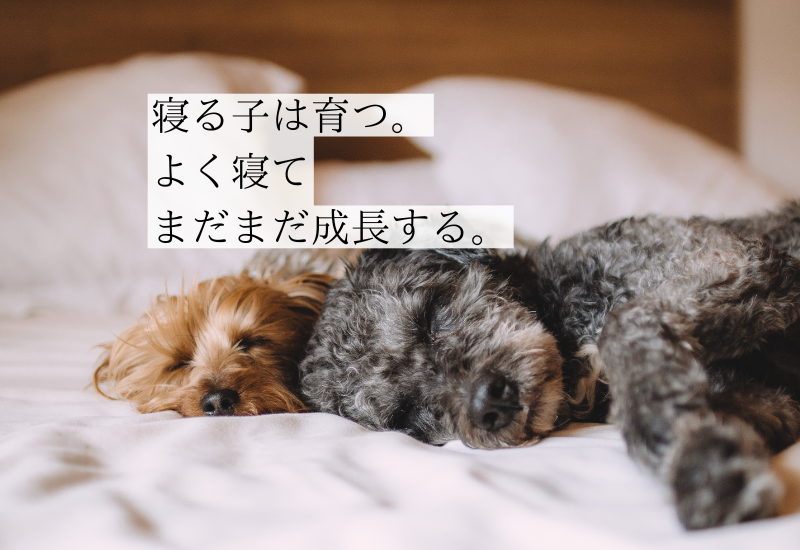
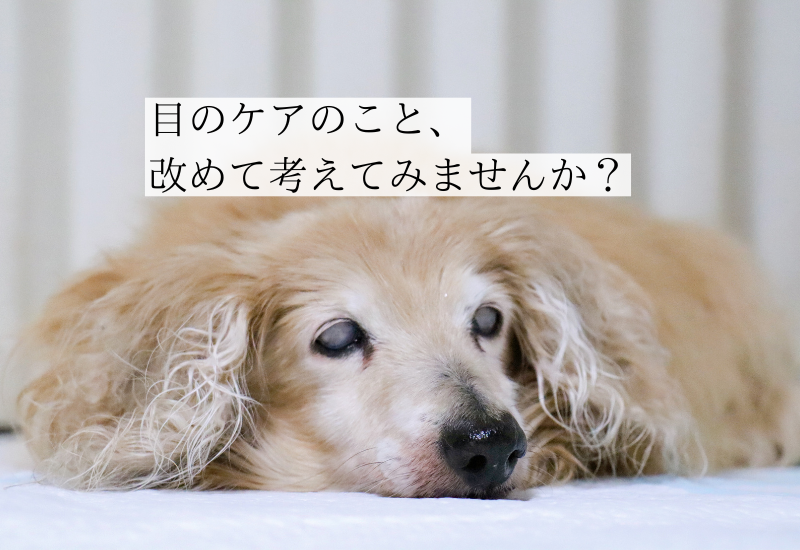
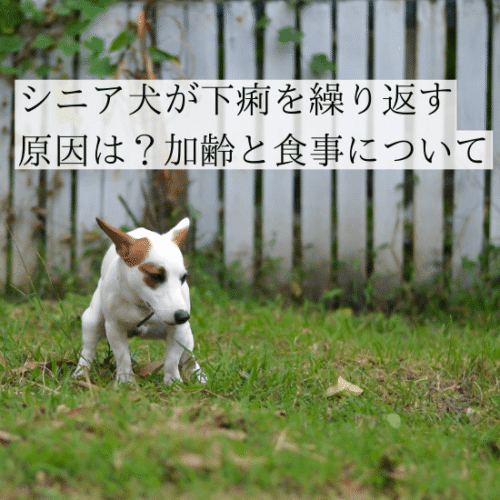

のシャンプーはどうする?頻度ややり方、注意点を解説-500x500.png)





この記事へのコメントはありません。