シニア犬の夜鳴き、病気のサイン?獣医師に相談すべきタイミングと家庭でできるサポート方法

シニア犬の夜鳴きに悩むママさん、パパさんは少なくありません。
静かな夜に鳴き声が響くと、愛犬も飼い主も眠れず、心身ともに疲れ切ってしまうこともあるでしょう。
しかし、夜鳴きは「わがまま」や「しつけの問題」ではなく、加齢にともなう体や心の変化が原因となることが多いのです。
放置せず、必要に応じて獣医師に相談することが大切です。
この記事では、シニア犬の夜鳴きの主な原因・獣医師へ相談すべきタイミング・家庭でできるサポート方法を分かりやすく紹介します。
シニア犬が夜鳴きをする主な原因3つ
.png)
夜鳴きには、年齢を重ねたことによる心や体の変化が関係しています。
その背景を知ることで、「どうして鳴くの?」という不安が少し和らぎ、対策も立てやすくなるはずです。
1. 感覚の衰えによる不安や混乱

聴こえづらくなったり、視界がぼんやりしてきたりすると、シニア犬はまわりの様子を正確に把握できなくなります。
暗くて静かな夜は、そんな不安がいっそう強くなる時間帯。
ママさん、パパさんの姿が見えなくなっただけでも、「どこに行ったの?」と落ち着かなくなることがあります。
甘えん坊なタイプの子ほど、その不安から鳴くことで表現する傾向があります。
とくに聴力や視力が衰え始めた頃は、環境の変化にも敏感になりやすいので注意が必要です。
2. 痛みや体の不調

夜間に鳴く理由が、体のどこかの痛みや違和感であるケースも少なくありません。
関節のこわばり、内臓の不調、便や尿が出にくいなど、シニア犬はさまざまな悩みを抱えていることも珍しくありません。
昼間は動いていることで気が紛れても、静かな夜になると痛みを意識しやすくなります。
「いつもより寝返りが多い」「体を触ると嫌がる」といった様子がある場合は、早めに動物病院を受診してみましょう。
シニア期は、病気のサインが分かりにくいことも多いため、夜鳴きが続くときは体のSOSの可能性もあります。
3. 認知症(犬の認知機能不全)

年齢とともに、脳の働きがゆるやかに変化していくことがあります。
その結果、昼夜の感覚が逆転したり、同じ場所をぐるぐる歩き回ったり、名前を呼んでも反応が薄くなることも。
こうした変化は、いわゆる「犬の認知機能不全(認知症)」のサインの一つです。
環境のちょっとした変化や、家族の不在といった“いつもと違うこと”がきっかけで夜鳴きが増える場合もあります。
日中は軽い散歩や日光浴で体内リズムを整え、夜は落ち着ける空間をつくるなど、規則正しい生活を意識するとよいでしょう。
シニア犬の夜鳴きで獣医師に相談すべきタイミングとチェックリスト
.png)
夜鳴きが続くと「そのうち落ち着くかも」と思いがちですが、実は体や心の不調が隠れていることもあります。
特に、夜鳴きが1週間以上続く、行動が昼夜逆転している、歩行が不安定になったなどの変化が見られる場合は、早めに獣医師へ相談しましょう。
チェックしておきたい項目
- 夜鳴きが1週間以上続いている
- 昼夜が逆転し、日中寝て夜に起きている
- 歩行が不安定・ふらつきがある
- 食欲が落ちている
- 排泄の失敗が増えた
- 痛みや違和感がありそう
- ぼんやりする時間が増えた
- 急に夜鳴きをするようになった
これらのサインは、認知症や前庭疾患、関節痛、視覚・聴覚の衰えなどの可能性を示している場合もあります。
早めの相談が、症状の進行をゆるやかにしたり、生活を楽にしたりする第一歩になります。
診察を受ける際は、「いつから」「どんな様子で」「どのくらいの頻度で鳴くか」を具体的に伝えると、診断がスムーズです。
私は実際に、夜鳴きの様子を動画に撮って獣医師に見せたことがあります。
言葉だけでは伝わりにくい動きや表情を確認してもらえるため、より正確な診断や適切なアドバイスにつながりました。
気づいたときに短い動画を撮っておくのもおすすめです。
獣医師からは、状況に応じてサプリメント、漢方、リハビリ、必要に応じた薬など、体への負担を抑えた方法を提案されることもあるでしょう。
「シニア犬だから仕方ない」と思わず、まずは専門家の目で確認してもらうことが大切です。
家庭でできるシニア犬の夜鳴き対策5つ
.png)
夜鳴きを和らげるには、「愛犬が安心できる環境づくり」が何よりも大切です。
動物病院での診断と並行して、家庭でも環境を整えてあげましょう。
ここでは、すぐに始められる5つのポイントを紹介します。
1. 環境を安心できる空間に整える

シニア犬が安心して眠れる場所をつくることは、夜鳴き対策の基本です。
- ママさん、パパさんの気配を感じられる場所にベッドを置く
- ほんのり明かりをつけて真っ暗にしない
- 外の音が気にならないよう遮音カーテンを使う
- 静かなBGMを流す
こうした小さな工夫で、不安からくる夜鳴きが和らぐことがあります。
シニア犬は感覚が衰え、暗闇や小さな物音に敏感になるため、安心できる「静かな明るさ」がポイントです。
とくに季節の変わり目は、室温の変化も夜鳴きの一因になります。冷えや暑さを防ぐ寝具選びも見直してみましょう。
2. 日中の活動量を増やす
①.png)
日中によく動けていないと、夜の眠りが浅くなりがちです。
散歩が難しい場合でも、室内でおもちゃを使った軽い運動や、ママさん、パパさんとのアイコンタクト遊びを取り入れましょう。
また、ずっと家の中にいるよりも、抱っこ散歩で外の空気に触れるだけでも気分転換になるでしょう。
犬用の歩行補助ハーネスや車いすを使うのも一つの選択肢としておすすめです。
3. 食事の見直し

食事内容やタイミングを見直すだけでも、夜鳴きを和らげられる場合があります。
シニア期になると、咀嚼(そしゃく)する力や消化機能が少しずつ衰えてくると言われています。
私が一緒に暮らしていた愛犬も、咀嚼力が弱くなってからは、ずっと食べていたドライフードを残すようになりました。
そこで、ウェットフードに切り替えたり、消化しやすい具材で手作りごはんを作ったりと、できる範囲で調整しました。
食べやすくなることでお腹が空いて夜鳴きが減り、朝まで眠れるようになるシニア犬もいます。
4. 頼れる仲間とつながる
②.png)
シニア犬の夜鳴きに対応するのは、想像以上に根気が必要です。ひとりで抱え込まず、頼れる人やサービスを活用しましょう。
- 夜間や外出時に頼めるペットシッター
- シニア犬に慣れたペットサロンのスタッフ
- 同じ悩みを共有できるSNSやオンラインコミュニティ
- 愛犬をよく知る友人・家族
孤独を感じがちな介護期こそ、信頼できる仲間の存在が心の支えになります。
小さな悩みでも話せる相手がいることで、気持ちの整理がつきやすく、前向きにお世話を続けられます。
決して「自分ひとりで頑張らなきゃ」と思いすぎず、支え合うケアのかたちを見つけていきましょう。
5. スキンシップと声かけを忘れずに

夜鳴きが始まったときは、焦って叱らず、落ち着いた声で「大丈夫だよ」と伝えましょう。そっと体に触れるだけでも安心できるシニア犬もいます。
小さな変化を見つけて「今日も頑張ったね」と褒めることが、心の安定につながります。
そして、鳴かない夜があった日は「今日はゆっくり眠れたね」と一緒に喜びましょう。
シニア犬にとって、ママさん、パパさんの安心した声や笑顔は、何よりの薬になります。
まとめ
.png)
夜鳴きが続くと、どんなに元気なママさん、パパさんの心も疲れてしまいます。しかし、夜鳴きは「老いのサイン」であり、愛犬からの「助けを求めるサイン」でもあるのです。
完璧な介護を目指すよりも、「今日はここまでできた」と自分にも優しくしてあげましょう。
ときには家族やペットシッターに頼って、ママさん、パパさん自身の休息も大切にしてください。
夜鳴きの悩みは、誰にでも起こりうる自然な過程です。
「どうして鳴くの?」と焦るよりも「何を伝えようとしているのかな?」と受け止めること。
焦らず、専門家や仲間の力を借りながら、少しずつ“わが家流の介護スタイルを見つけていきましょう。
夜鳴きの向こうにあるのは、「まだあなたと一緒にいたい」という愛犬の気持ちです。寄り添いながら、シニア期の毎日を穏やかに過ごしていきましょう。

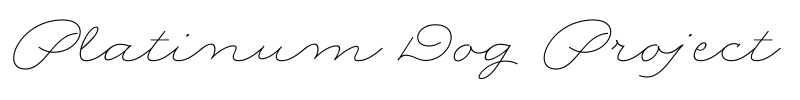
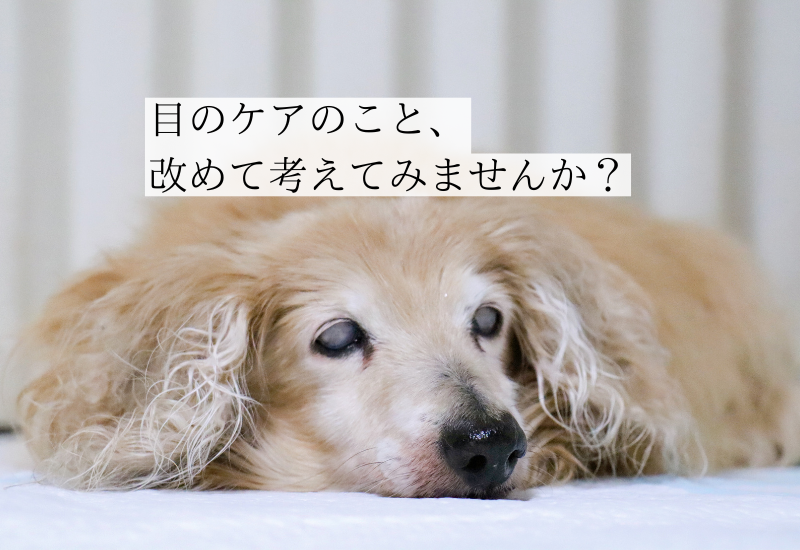
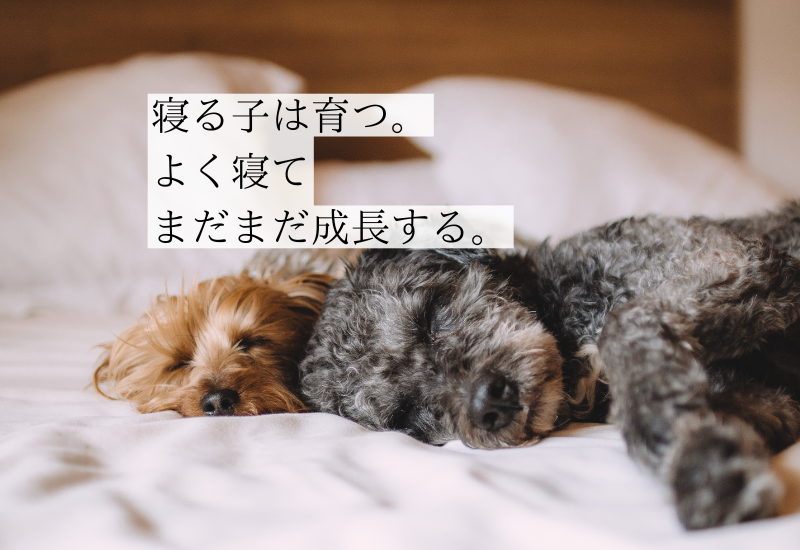






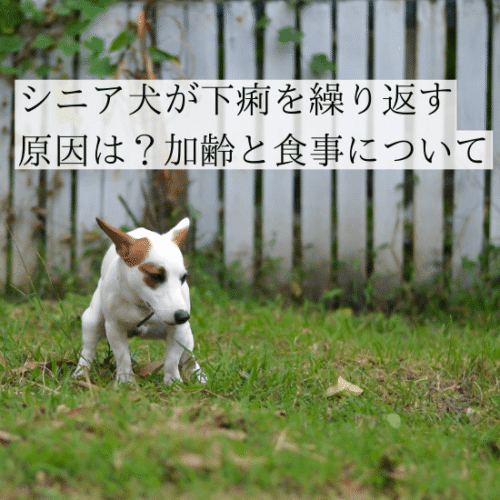

この記事へのコメントはありません。