シニア犬の息が荒いときの異常の見分け方!原因と受診の目安、対処法を解説

愛犬の息が「ハァハァ」と荒くなっていると心配になりますよね。
私自身、愛犬がプラチナ期(ハイシニア期)であり、突然「ハァハァ」と呼吸する姿を見て不安になったことがあります。
実はシニア期は体力や臓器の働きが低下しているため、病気以外の原因でもすぐに息が荒くなることがあります。ただもちろん、病気が理由であることもあるので、そのままにしておくのはよくありません。
今回は、シニア期の愛犬の息が荒くなる原因と対処法、すぐに受診すべきサインをわかりやすく解説します。
シニア犬の息が荒い?正常な呼吸との違いを確認

シニア犬になると、体力の衰えなどでちょっとした動作でも息が速くなったり、呼吸が荒く見えたりすることがあります。
そのため呼吸が荒くなるのは必ずしも異常とは限らないのですが、正常な呼吸との違いを見極めることが大切です。
正常ではない呼吸の例
- 呼吸時に「ヒューヒュー、ゼイゼイ」という異音がある
- お腹(腹部)が膨らんだり凹んだりしている(腹式呼吸的動き)
- 呼吸が明らかに苦しそう(肩で息をする、胸部が激しく動くなど)
- 息が荒くよだれを垂らしている
- 息が荒く震えている
- 息が荒く、口を開けて上を向くように呼吸する
一方で正常な呼吸とは、鼻で静かに呼吸をしている状態です。胸の上下運動も穏やかでリズミカルであり、呼吸に伴って肩や腹部が大きく動いたり、呼吸時に音がすることはありません。安静時の胸の上下数は1分間に15〜30回程度が目安です。※体格や気温などによっても異なります。
また、暑さ・興奮・緊張・ストレスなどにより、舌を出して口で呼吸をしている場合も異常ではありません。こういった場合はしばらく休むと落ち着き、呼吸音も静かであることが特徴です。
もし度々愛犬の息の荒さが気になるようであれば、安静時の呼吸数を測っておくと、異常な呼吸かどうか判断しやすくなります。
シニア犬の息が荒い!すぐに動物病院へ行くべき症状

愛犬の息が荒いだけでなく、次のような症状がある場合は緊急受診レベルです。すぐに動物病院へ向かいましょう。
すぐに受診が必要な症状
- 安静時でも呼吸が速く、浅い
- 舌や歯ぐきが紫色(チアノーゼ)
- 咳が止まらない
- 横になれない(立ったまま動けない)
- 意識がぼんやりしている
- 食欲・元気が極端に低下している
これらは心不全や呼吸不全のサインかもしれません。動物病院へ連絡し、できるだけ安静な姿勢を保ちながら向かいましょう。
シニア犬の息が荒い主な原因を6つ紹介

それでは、シニア犬の息が荒くなる主な6つの原因を詳しく見ていきましょう。
1. 体力や心肺機能の低下

加齢により筋力や心肺機能が衰えると、少し動いただけでも息が上がりやすくなります。また体温調節も苦手になるので、暑さや湿度の高さでも呼吸数が増えやすく、温度や湿度の管理が重要です。
息が荒いときは無理に散歩や運動をさせず、静かな場所で休ませましょう。また心臓や呼吸器に負担がかかる行動は控え、室温を20〜25℃前後、湿度は50%程度を保つよう心がけてください。
2. 心臓の病気(僧帽弁閉鎖不全症など)
-1.png)
シニア犬の呼吸の荒さで最も多い原因とも言えるのが心臓病です。特に小型犬では「僧帽弁閉鎖不全症」が多く、血液がうまく循環できずに肺に水がたまる「肺水腫」を引き起こすことがあります。
酸素をうまく取り込めず溺れているような感覚になるため、愛犬もとても苦しい状態です。できるだけ早めに動物病院を受診してください。
3. 呼吸器の病気(気管虚脱・肺炎など)
-1.png)
小型犬・中型犬では「気管虚脱」という病気も多く見られます。気管が押しつぶされるように変形し、空気が通りにくくなることで「ゼーゼー」「ガーガー」という呼吸音や咳が出ます。
また、感染症による肺炎・気管支炎などでも息が荒くなります。
4.貧血

シニア期では、慢性腎臓病や腫瘍、消化管出血などが原因で貧血が起こることがあります。貧血になると、血液中の酸素を運ぶ赤血球が減少し、体内に十分な酸素が行き渡りません。その結果、犬は酸素を取り込もうと呼吸数を増やし、息が荒くなることがあります。
特に、立ち上がるとすぐにハァハァしたり、舌や歯ぐきが白っぽい・ピンクが薄い場合は要注意です。呼吸の変化に加えて食欲や元気の低下が見られる場合は、早めに血液検査を受けることをおすすめします。
5. 痛みやストレス、不安、恐怖

犬はからだに痛みがあるときに呼吸が速くなります。たとえば関節痛や腹痛、体を動かすと痛むようなとき、また環境の変化や雷などの恐怖でもハァハァすることがあります。
シニア犬は身体機能と同様に感情のコントロールもうまくいかなくなっているので、些細なことでもストレスや不安、恐怖を感じやすいため注意しましょう。
6. 熱中症

シニア犬は体温調節が苦手で、少しの暑さでも体温が上昇しやすい傾向があります。特に夏場や暖房の効いた室内では注意が必要です。
ぐったりしていたり、よだれを大量に流している場合は命に関わる危険な状態です。すぐにからだを冷やして急いで動物病院を受診しましょう。
具体的には、日の当たらない涼しい場所に移動させ、水で濡らしたタオルを体全体にかけて風を当てます。
また、首やわき腹、内ももなどにハンカチを巻いた保冷剤を当てて体を冷やしましょう。ただし、冷やし過ぎには注意してください。
夜にシニア犬の息が荒いときの対処法

夜になるとシニア犬の息が荒い・寝ているときに息が荒い、といった様子が見られる場合、心臓や肺への負担が進んでいる可能性があります。
また、夜中に目覚めて歩き回ったりそわそわして落ち着かない様子は、横になれない苦しさが反映されていることもあるため注意が必要です。
できるだけ早く動物病院を受診し、「昼間と比較して夜にどう悪化するか」どうかをしっかりと獣医師に説明しましょう。
もともと体力のないシニア犬は、呼吸がしづらいことで睡眠不足が続くと体力を消耗してしまい大変危険です。
シニア犬の息が荒く震えを伴うときの対処法

シニア犬の息が荒く震えを伴う場合は、痛みや神経疾患、体温の異常が関与している可能性があります。愛犬がぐったりしているようであれば、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。
特に、寝ながら震えていたり震えながらよだれを出している場合には、てんかん発作や中枢神経の異常も考えられます。
愛犬を刺激しないようにテレビなどの音の出るものは消して、周りにぶつかるものがないよう安全な環境を作ります。
また早めに病院を受診する必要があるので、動物病院へ行くまでに、
- 震えはどれくらい続いているのか
- どこが震えているのか(前肢・後肢・全身)
などを確認して、診察の際に伝えるようにしましょう。慌ててしまいがちですが、震えている様子をスマホで録画しておくと診察の助けになります。
老犬の息が荒く、吠えたり動き回るときの対処法

多くの場合、息が荒い犬はじっとしていることが多いですが、吠える・歩き回るといった様子が見られるのであれば、不快感や痛みを表している可能性があります。
苦しい状態でじっとしていられず、吠えてママさんやパパさんを呼ぼうとしたり、苦しくてじっとしていられずに動き回ったりしているのかもしれません。
動き回っているときに物にぶつかって怪我をしたり転んだりしないように、愛犬の周りの安全を確保しましょう。
そして無理に押さえつけたりはせず、愛犬が落ち着いたら早めに動物病院を受診するようにします。また、できれば愛犬の様子をスマホで録画しておくと診察がスムーズです。
シニア犬の息が荒く、水を良く飲むときの対処法

シニア犬が息が荒く、水をよく飲むようになった場合、心臓や腎臓、内分泌系(ホルモン)の機能が低下している可能性があります。
特に心臓病や腎不全、糖尿病などでは「息が荒い」「多飲多尿」といった症状が見られるので、まずは落ち着ける静かな環境を整え、いつでも新鮮な水を飲めるようにしてあげましょう。
また水を飲む頻度や量を記録しておき、早めに動物病院を受診するようにしてください。
食後にシニア犬の息が荒い・息が荒いのに口を閉じているときの対処法

食後は胃が膨らんで横隔膜を圧迫し、一時的に呼吸がしづらくなることがあります。
これは軽度で一過性であれば問題ないこともありますが、頻繁に起こる場合は胃拡張や消化器疾患が関与している可能性があります。
また、口を閉じているのにシニア犬の息が荒いときは、心臓や肺に負担がかかっているサインかもしれません。できるだけ早めに動物病院を受診しましょう。
まとめ

シニア犬の息が荒くなるのは、単なる加齢変化のこともありますが、心臓・呼吸器・体温調節などの異常が隠れている可能性も高いです。
特に「安静時にも息が荒い」「咳がある」「舌が紫っぽい」などのサインがあるときは、迷わず病院へ行きましょう。
ママさん、パパさんが毎日の変化に気づき、早めに対応することが愛犬の命を守ることにつながります。
また、半年に1回は健康診断を受け、肥満にならないよう食事を管理し、シニア犬にストレスのない環境で、穏やかな毎日を過ごせるようにしてあげてくださいね。

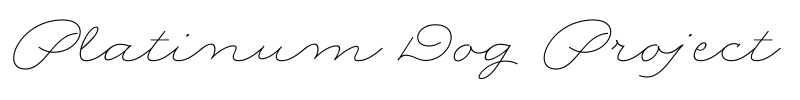

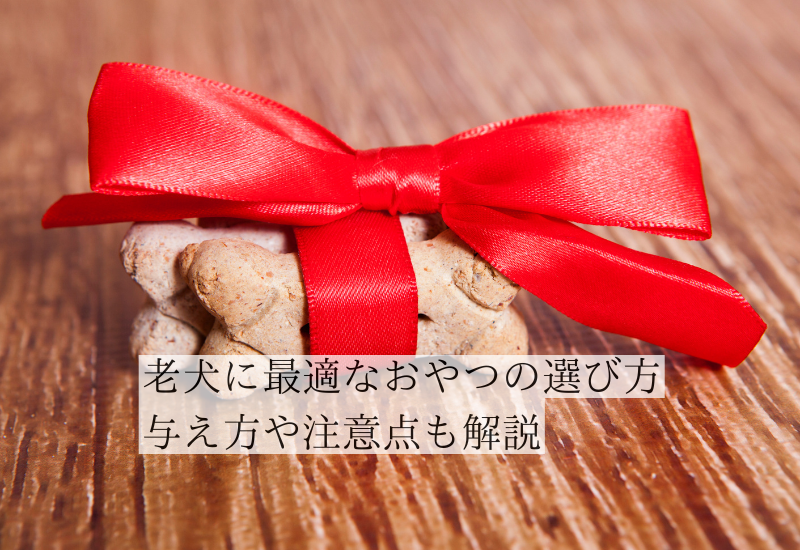










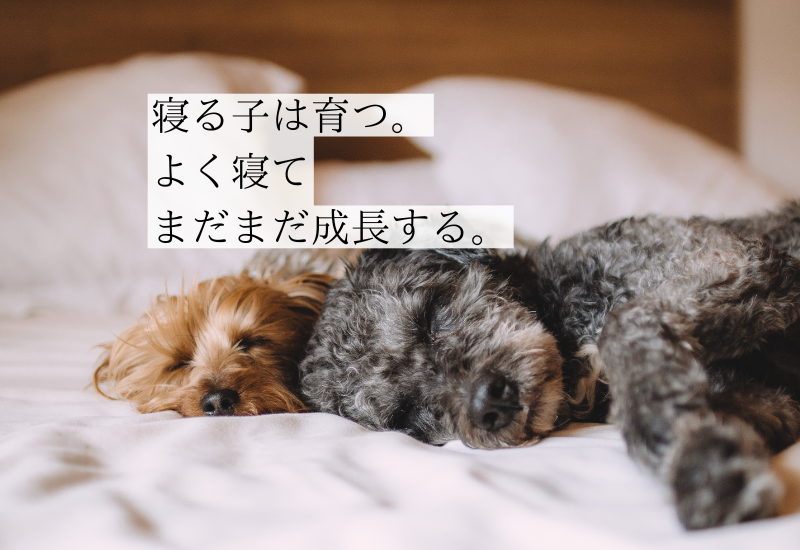
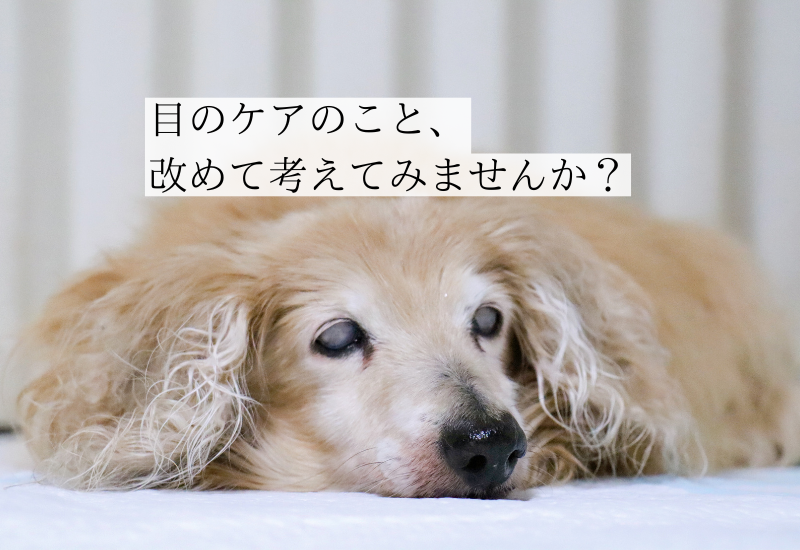








この記事へのコメントはありません。