シニア犬が寝てばかりなのはなぜ?原因からサポート方法まで解説

愛犬がシニア期に入り、若い頃と比べて寝ている時間がとても長くなったと感じていませんか?
かつては元気に走り回っていた愛犬が1日中寝ている姿を見ると、「どこか具合が悪いのでは?」「もうお別れが近いのでは…」と、不安に感じるママさんパパさんは少なくありません。
多くの場合、シニア犬(老犬)が寝てばかりになるのは、加齢に伴う自然な変化です。
大切なのは、その「寝てばかり」が老化の範囲内なのか、注意すべき異常のサインなのかを見極めてあげることです。
この記事では、シニア犬が寝てばかりになる理由からシニア犬の平均的な睡眠時間、危険なサインの見分け方、ママさんパパさんができるケア方法まで解説します。
シニア犬が「寝てばかり」なのはなぜ?考えられる4つの理由
.png)
愛犬が寝てばかりになる背景には、一つの理由だけでなく、複数の要因があることがほとんどです。
まずは、シニア犬が寝てばかりいる主な4つの理由を見ていきましょう。
①老化による体力の低下

シニア犬が寝てばかりになるときに最も考えられるのは、加齢による体力の低下です。
人間と同じように、犬も歳を重ねると基礎代謝が落ち、筋力も徐々に低下します。
そのため、若い頃と同じように活動することが難しくなり、少し動いただけでも疲れやすくなるのです。
体力を回復させる、または温存するために、自然と睡眠時間が長くなっていくと考えられます。
これは多くの場合、病気ではなく自然な老化現象といえるでしょう。
②認知機能の低下

人間でいう「認知症」が、犬にも起こることがあります。
認知機能が低下すると、脳の活動リズムが乱れ、昼夜逆転の症状が出やすくなります。
日中はぼーっとしたり寝てばかりいたりするのに、夜になると起きてしまい、夜鳴きや徘徊が始まるケースも少なくありません。
③季節や環境変化

シニア犬は、若い頃に比べて体力が低下し、季節の変わり目や環境の変化によるストレスの影響を受けやすくなります。
とくに夏の暑さや冬の寒さは、体温調節機能が衰えたシニア犬にとって大きな負担です。
体力を消耗しやすくなり、寝てばかりになる場合があります。
また、引っ越しや家族構成の変化やママさんパパさんの生活リズムの変化などもシニア犬にとってはストレスとなり、体調を崩して寝込む原因になることがあるので注意しましょう。
④痛みや病気による不調

とくに注意が必要なのは、体のどこかの「痛み」や「病気」によって愛犬が寝てばかりいることです。
関節炎や椎間板ヘルニアなどは、立ち上がったり歩いたりする動作自体が苦痛になり、寝床でじっとしている時間が増えます。
また、心臓病や呼吸器疾患がある場合、少し動くだけで息切れしたり、咳が出たりする場合があり、活動を避けて寝てばかりになるケースもあります。
寝てばかりいると同時に、食欲の低下や体を庇っている様子などが見られた場合は、体調不良を疑いましょう。
シニア犬(老犬)の平均睡眠時間は?

「寝てばかり」と言っても、シニア犬はどれくらい寝るのが普通なのでしょうか。
個体差はありますが、成犬の平均睡眠時間が1日あたり約12〜14時間なのに対し、シニア犬(老犬)の平均睡眠時間は、1日あたり18〜20時間とされています。
シニア犬は、深い眠り(ノンレム睡眠)が減り、浅い眠り(レム睡眠)の割合が増える傾向です。
そのため、物音ですぐに目を覚ます一方で、全体的な睡眠時間は長くなります。
シニア犬が1日の大半を寝て過ごしていても、異常というわけではありません。
大切なのは睡眠時間の「長さ」だけでなく、「睡眠以外の様子」に変化がないかを確認することです。
シニア犬が寝てばかりでも大丈夫?4つの異常サインと見分け方

寝ている時間が長くても、「食欲旺盛」「散歩(短時間でも)に行きたがる」「表情が穏やか」であれば、老化の範囲内である可能性が高いです。
しかし、以下のような症状が見られる場合は、病気や重篤な体調不良が隠れている可能性があります。
|
それぞれの症状について詳しく解説します。
①食欲がなく水も飲まない

わかりやすい危険なサインの一つが「食欲の低下」です。
シニア犬にとって、食事と水分補給は体力を維持するために大切です。
|
このような状態は、脱水症状や栄養失調を引き起こすだけでなく、内臓疾患、重度の痛み、感染症、腫瘍などのさまざまな病気の可能性があります。
②呼吸がおかしい(速い、苦しそう、咳き込む)

寝ているときの呼吸が異常に速い場合や、異常な呼吸音がする場合、苦しそうに咳き込む場合は、心臓疾患や呼吸器疾患の可能性があります。
愛犬がリラックスしているときの呼吸の速さは1分間に40回以上が目安とされています。
愛犬の呼吸に異常がないかどうか、定期的にチェックしましょう。
③体の特定の部分を痛がる、震えている

「キャン!」と鳴かなくても、以下のような行動が見られる場合は、体に痛みを感じている可能性があります。
|
関節炎、椎間板ヘルニア、腹部の内臓疾患(膵炎など)による強い痛みが原因と考えられます。
④起こしても起きない、ぐったりしている

呼びかけたり、体に触れたりしても反応が鈍い、あるいは全く起きない状態は、意識レベルが低下している可能性があり危険な状態です。
反応しないと同時に失禁している、体に力が入っていないなどの症状が見られる場合は、脳疾患や極度の低血糖、ショック状態など、緊急性の高い状態が考えられます。
すぐに動物病院を受診しましょう。
寝てばかりのシニア犬(老犬)への正しい接し方

愛犬が寝ている時間が長くなると、「このままずっと寝たきりになるのでは」「少しは起こして運動させた方がいいのでは」と焦ってしまうかもしれません。
しかし、シニア犬にとって寝ることは体力を回復するために大切です。
そのため、愛犬の睡眠を邪魔しないような配慮が必要です。
ここでは、ママさんパパさんが意識したいシニア犬への接し方のポイントを3つ紹介します。
基本は無理に起こさない

シニア犬にとって睡眠は、体力を回復・温存するための重要な時間です。
とくにぐっすりと眠っているときは、無理に起こすべきではありません。
睡眠を妨げられること自体がストレスになり、かえって体力を消耗させてしまう可能性があります。
愛犬のペースを尊重し、穏やかに休ませてあげましょう。
急に触らない

シニア犬は、聴力や視力が衰えていきます。
そのため、寝ているときにいきなり体に触れると、驚かせてしまいます。
驚きのあまりパニックになったり、心臓に負担がかかったり、反射的にママさんパパさんを噛んでしまったりすることもあるでしょう。
寝ている愛犬には、声をかけたりニオイを嗅がせたりしてから触れると、驚かせずに済みます。
起こすときは優しく起こす

眠っている愛犬を起こさないようにしても、食事や排泄の介助、床ずれ防止のための体位変換(寝返り)など、どうしても起こさなければならないときもあります。
その際は、上記でも説明したように、声をかけたりニオイを嗅がせたりしてから優しく触れるようにしましょう。
寝てばかりのシニア犬(老犬)にできる4つのケア
.png)
寝る時間が長くなったシニア犬でも、ママさんパパさんがケアを工夫することで、愛犬の生活の質を改善できます。
ここからは、シニア犬が快適に過ごすための4つのサポート方法を紹介します。
①快適な睡眠環境を整える
.png)
シニア犬が1日の大半を過ごす寝床の環境は、快適に整えることが不可欠です。
寝床の場所は、ママさんパパさんの気配が感じられる、静かで落ち着ける場所が理想です。
直射日光が当たらず、エアコンの風が直接当たらない場所に設置しましょう。
また、シニア犬は体温調節が苦手です。室温は夏場なら25度程度(クーラー)、冬場なら20〜23度程度を目安に保ちましょう。
ベッドは適度な硬さがあり、体圧を分散できる高反発マットがおすすめです。
②床ずれを防ぐ

自力で寝返りを打つのが難しい場合は、「床ずれ」に注意が必要です。
床ずれは、同じ体勢で寝続けることで、骨が出っ張った部分(頬、肩、腰、足の関節など)の血流が滞り、皮膚や組織が壊死する状態です。
床ずれを予防するには、2~3時間おきを目安に愛犬の寝返りを介助してあげましょう。
優しく体を撫でたり、関節を軽く曲げ伸ばししたりなどのマッサージも床ずれ予防に効果的です。
③水分補給と食事で体力を維持する

寝てばかりいると、自分で水やご飯を食べに行く回数も減りがちです。
水分補給の回数を増やしてほしい場合は、寝床のすぐそばに新鮮な水を置くとよいでしょう。
自分から水を飲まない場合は、いつもの食事に水を入れて与えるのもおすすめです。
食欲が落ちている場合は、フードを少し温めて匂いを立たせたり、ウェットフードやペースト状の栄養食を試したりしてみてください。
④適度な刺激で生活リズムを整える
.png)
体力低下や認知機能低下で寝てばかりいる場合は、生活の中に適度な「刺激」を取り入れ、生活リズムを整えることが大切です。
天気の良い日は、ベランダや窓際で5分〜10分でも日光浴をさせましょう。
体内時計がリセットされ、昼夜逆転の防止に役立ちます。
また、歩けなくてもペットカートや抱っこで外に連れ出し、外の空気や音、匂いを感じさせてあげることも脳への良い刺激となります。
まとめ|シニア犬が寝てばかりでも慌てず、穏やかな毎日をサポートしよう

シニア犬(老犬)が寝てばかりになるのは、多くの場合、体力が低下したことによる自然な老化現象です。
しかし、関節の痛みや内臓疾患、認知症などが原因で、寝てばかりいる可能性もあります。
大切なのは、「食欲がない」「呼吸がおかしい」「起こしても起きない」といった老化だけでは説明できない異常のサインを見逃さないことです。
愛犬が寝てばかりいると不安になりますが、まずは慌てずに愛犬の様子をよく観察しましょう。
たとえ寝ている時間が長くても、床ずれを防ぎ、快適な環境を整えることで愛犬の生活の質を高められます。
愛犬との穏やかな時間を大切に、毎日をサポートしてあげましょう。

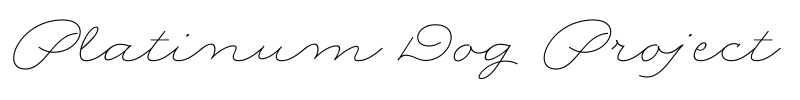


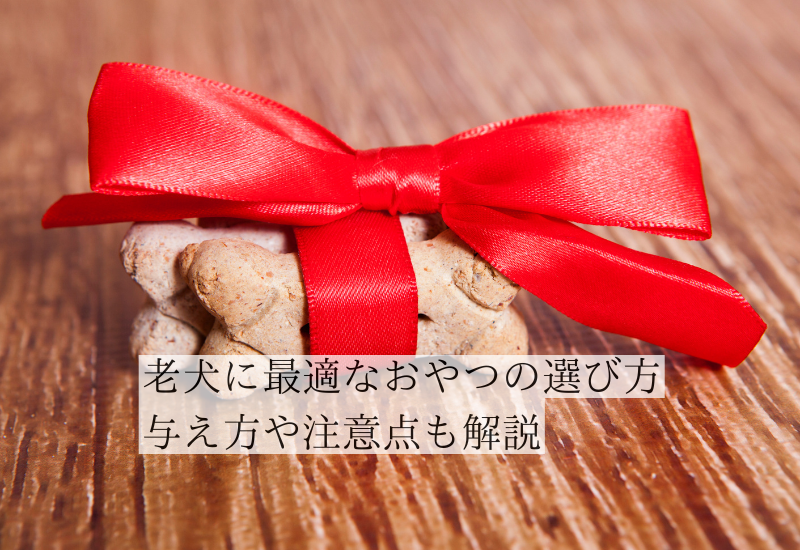


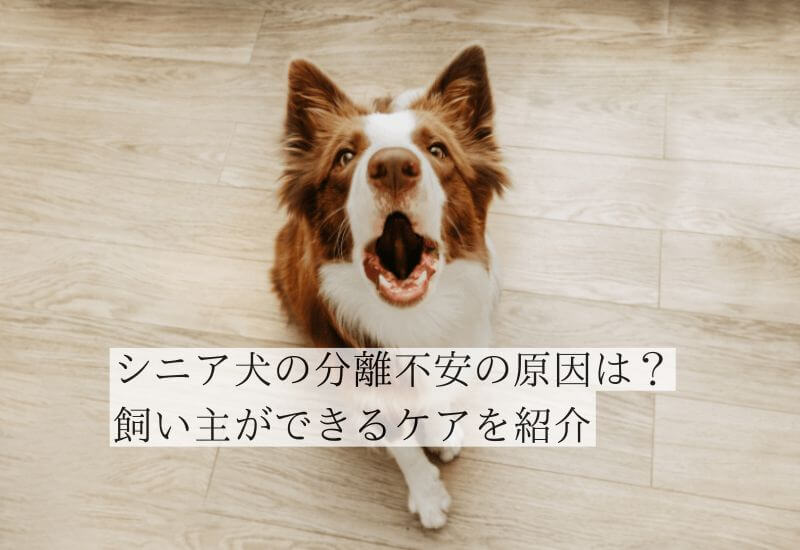








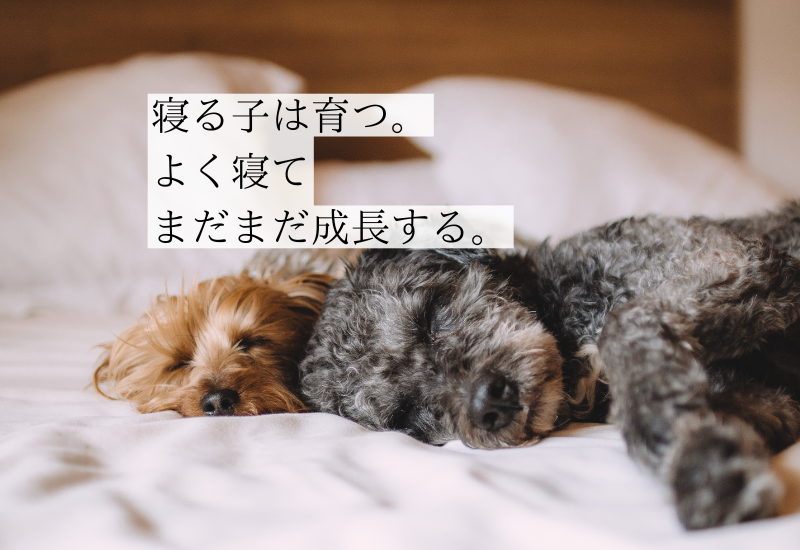
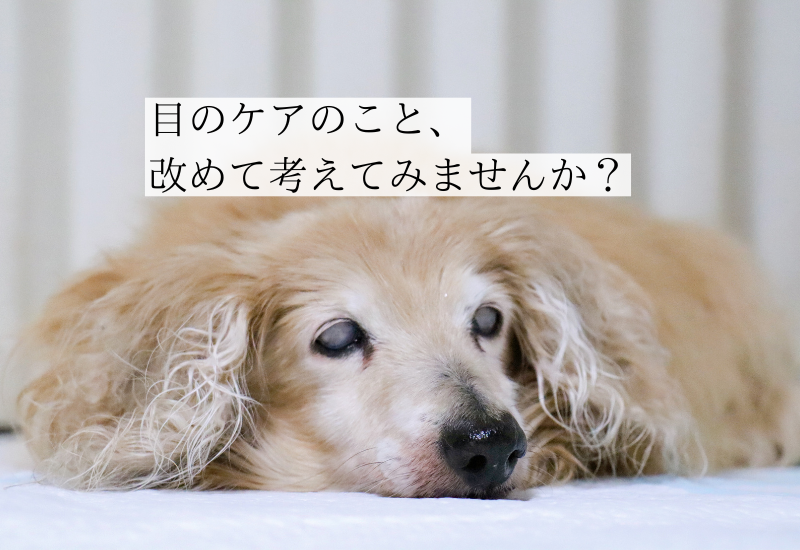





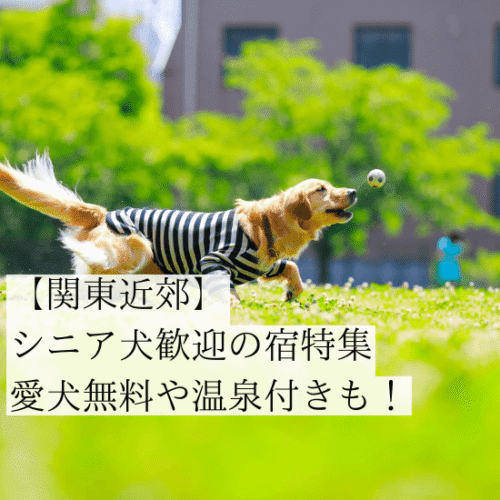


この記事へのコメントはありません。