シニア犬の耳が遠い?聞こえにくくなったときのサインと接し方

愛犬がシニア期に入り、「名前を呼んでも反応が鈍くなった」「ぐっすり寝ていて物音に気づかない」といった姿に、「耳が遠いのでは?」と不安になっていませんか。
シニア犬の聴力低下は多くの場合、加齢による自然な変化です。
しかし、中には治療可能な病気が隠れていたり、認知症の進行に関わったりする可能性もあります。
この記事では、シニア犬の難聴のサインから考えられる原因、耳が遠い愛犬と安心して暮らすための具体的な対処法まで解説します。
シニア犬の耳が遠いときに見られる4つのサイン

シニア犬の難聴は多くの場合、数年かけてゆっくりと進行します。
そのため、毎日一緒に過ごすママさんパパさんでも気づきにくいでしょう。
「あれ?」と思ったら、以下のようなサインがないか確認してみてください。
|
①呼んでも反応が鈍い・気づかない

以前は、名前を呼んだり、「おやつ」「散歩」といった大好きな言葉を聞いたりすると、すぐに喜んで飛んできたはずが、反応が鈍くなってきたと感じたら難聴を疑いましょう。
最初は遠くからの呼びかけや、小さな声に反応しなくなることが多いとされています。
進行すると、すぐそばで大きな声で呼ばないと気づかなくなります。
②小さな物音に気づかない

聴力が低下すると、生活の中の小さな物音に対する反応も薄くなりがちです。
|
以前なら敏感に反応していたはずの上記のような音に気づかず、ぐっすり寝続けていることが増えたら、耳が遠くなっているサインかもしれません。
③急に触ると驚く

耳が遠くなった愛犬は、ママさんパパさんが近づいてくる足音や気配に気づくことができません。
そのため、寝ているときや何かに集中しているときに、急に体に触れられると驚いて飛び上がったり、恐怖心から噛みついたりしてしまう場合があります。
これは愛犬の性格が変わったのではなく、聞こえないことによる不安と驚きが原因といえるでしょう。
④不安そうにしている

聴覚は、犬が周囲の状況を把握するための重要な情報源です。
その情報が閉ざされると、愛犬は大きな不安を感じるようになります。
たとえば、以下のような行動が見られます。
|
このような行動の変化は、聴力低下による不安感が原因であるケースが少なくありません。
愛犬が本当に聞こえていないか確認する方法
.png)
シニア犬を呼んでも反応しない場合、「本当に聞こえていない」のか、それとも「聞こえているけどマイペースで無視している」のか、判断に迷うこともあるかもしれません。
ここでは、自宅でできる簡単なチェック方法と、混同しやすい認知症との違いを解説します。
自宅でできる簡単な聴力チェックの方法

愛犬が難聴かどうか確認したい場合は、以下の聴力チェックを試してみてください。
|
もし大きな音にも反応しない場合は、難聴がかなり進んでいる可能性があります。
ここで紹介した聴力チェックの方法は、あくまで簡易的なものです。
愛犬の耳が本当に遠くなっているかどうかを正確に診断するためにも、動物病院で検査を受けましょう。
難聴と混同しやすい認知症の症状

シニア犬が呼んでも来ない場合、難聴ではなく「認知症」の可能性もあります。
この2つは症状が似ており、併発するケースも多いとされています。
<難聴(聴覚の問題)の症状>
|
<認知症(脳の問題)の症状>
|
認知症の場合は夜鳴きや徘徊、部屋の隅や狭い場所で行き止まって動けなくなるなど、難聴には見られない症状が特徴的です。
難聴で音の刺激が減ると脳の働きが低下し、結果的に認知症の進行が早まるといわれています。
どちらか一方と決めつけず、両方の可能性を視野に入れて獣医師に相談しましょう。
シニア犬の耳が遠いのはなぜ?老化と急な病気の見分け方
.png)
愛犬の耳が遠いと感じたら、その原因が「老化」なのか、「病気」なのかを見極めることが大切です。
ここでは、耳が遠い原因を見極める方法を見ていきましょう。
加齢による聴力の低下(老齢性難聴)

シニア犬の難聴のほとんどは、加齢によって音を感じ取る神経が変性・衰弱していく「老齢性難聴」です。
これは人間が高齢になると耳が遠くなるのと同じ、自然な老化現象の1つです。
一般的に7歳〜10歳頃から徐々に症状が出始めるといわれています。
数年かけてゆっくりと進行するため、愛犬の耳が遠いと気付きにくいのが特徴です。
急に聞こえなくなった場合に疑うべき病気

「昨日までは聞こえていたのに、今日になったら急に反応がなくなった」という場合は、老化ではなく、以下のような病気が隠れている可能性があります。
|
急に聞こえなくなったときは、上記のような病気を疑い、早めに動物病院を受診しましょう。
シニア犬の難聴は治る?回復と治療の可能性

シニア犬の耳が遠くなったとき、治るのかどうか気になるママさんパパさんは多いのではないでしょうか。
治るかどうかは、耳が遠くなった原因によって異なります。
ここでは、シニア犬の難聴の治療について見ていきましょう。
老化(老齢性難聴)の場合:聴力の回復は難しい
.png)
残念ながら加齢によって衰えてしまった聴神経を、現在の医療で回復させることは難しいとされています。
老化によって耳が遠い場合は治療ではなく、これ以上悪化させないためのケアに力を入れましょう。
愛犬が不安を感じないように、ママさんパパさんが接し方や飼育環境を工夫することが大切です。
病気が原因の場合:早期治療で回復・改善する可能性

一方で、聞こえなくなった原因が病気であった場合、病気を早期に治療すると聴力が回復・改善する可能性があります。
たとえば、外耳炎・中耳炎の場合は耳の洗浄や点耳薬、内服薬などによる治療で炎症が治まり、耳垢や膿がなくなれば音が聞こえやすくなります。
また、異物や腫瘍が原因の場合、内視鏡や外科手術で取り除くと、聴力が回復するでしょう。
まずは動物病院で原因を特定することが大切

愛犬の難聴サインに気づいたら、自己判断で「老化だ」と決めつけず、まずは動物病院を受診しましょう。
動物病院では、耳の内部を確認する検査や、必要に応じて「BAER検査(脳幹聴覚誘発反応)」などの聴力検査を行い、耳や脳の異常を調べます。(※1)
その結果、シニア犬の耳が遠い状態が回復する見込みがあるのかどうかを判断でき、ママさんパパさんができるケア方法のアドバイスももらえます。
耳が遠いシニア犬と暮らすための工夫と接し方
.png)
耳が遠いシニア犬と暮らす場合、ママさんパパさんが接し方や飼育環境を工夫することが不可欠です。
ここからは、耳が遠い愛犬と暮らすための工夫を3つ紹介します。
ハンドサインを使う

声が届かなくても、目が見えている場合は「ハンドサイン(手の合図)」でコミュニケーションを取れます。
たとえば、「おすわり」「まて」「よし」などの基本的な指示は、声と同時に「決まった手の動き」で教えましょう。
耳が遠くなる前から、声とハンドサインをセットで教えておくのが理想です。
ママさんパパさんと愛犬との新しい「共通言語」を作るゲームだと思って、根気よく楽しんで取り組んでみてください。
後ろから急に触らない

耳が遠いシニア犬と暮らす際には、安全対策が不可欠です。
なかでも、背後からの急に触ることは「不意打ち」になり、強いストレスと恐怖を与える可能性があります。
これが続くと、ママさんパパさんの手に対して恐怖心を抱いたり、防衛的に噛みついたりするようになる場合もあります。
愛犬に近づくときは、必ず正面に回り込み、愛犬がママさんパパさんの存在を認識してから、優しく体に触れるようにしてください。
寝ている愛犬を起こすときは、まずは鼻先にママさんパパさんの手をそっと近づけて「嗅覚」で気づかせるとよいでしょう。
振動で合図を送る

振動で愛犬に合図を送る方法は、耳が遠くても理解しやすい方法です。
たとえば、耳が遠い愛犬が離れた場所で寝ているときに注意を引きたい場合、床を少し強く叩いて「振動」で存在を知らせます。
また、この振動の合図はご飯の合図としても使用できます。
まとめ|耳が遠くなったシニア犬も、安心できる暮らしを支えよう

シニア犬の耳が遠いのは、多くの場合、加齢による自然な老化現象です。
しかし、「歳だから仕方ない」と放置してしまうと、愛犬は聞こえない状態にストレスや不安を感じ、認知症の進行が早まってしまう可能性もあります。
まずは、耳の病気が隠れていないかを動物病院で確認し、加齢による難聴と診断されたら飼育環境や接し方を工夫しましょう。
ママさんパパさんの愛情を伝え続け、愛犬がストレスや不安を感じにくい暮らしを支えてあげることが何よりも大切です。
<参考文献>
※1参考:公益社団法人日本獣医師会「内耳疾患を疑う犬における聴性脳幹誘発反応の有用性の検討」

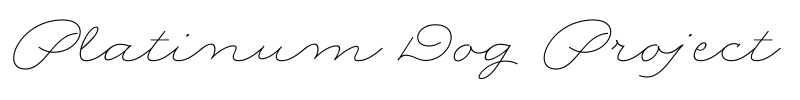


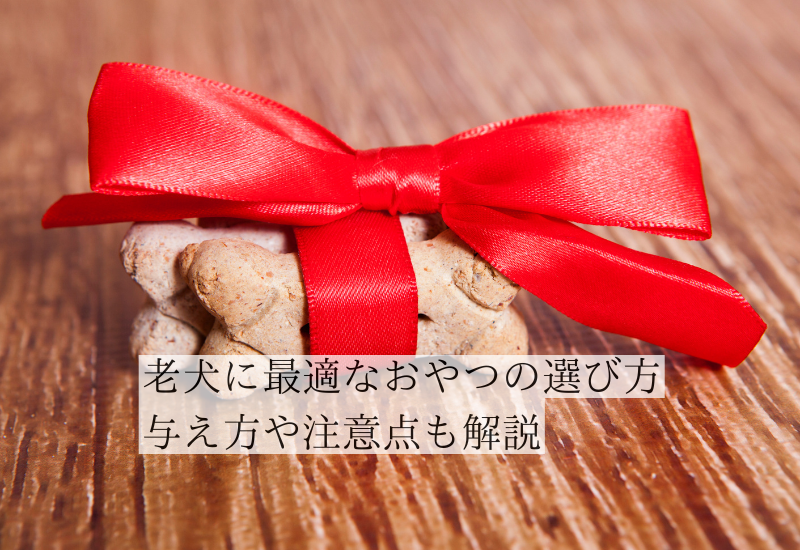



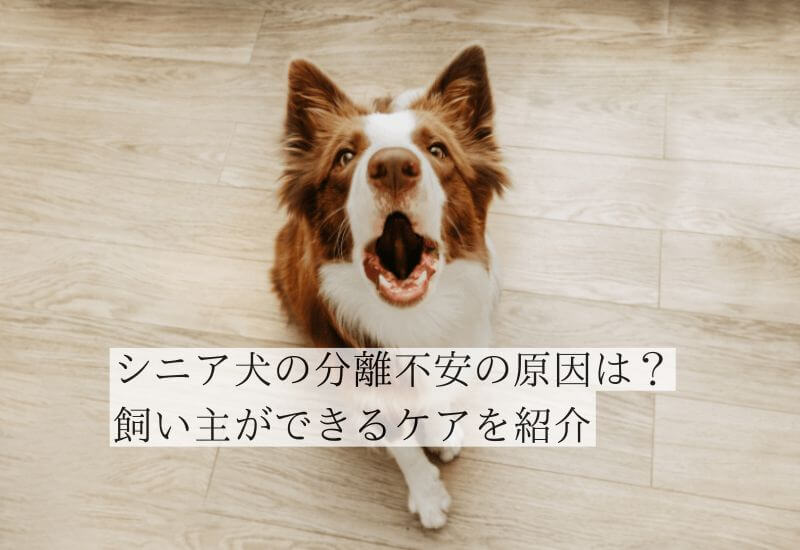







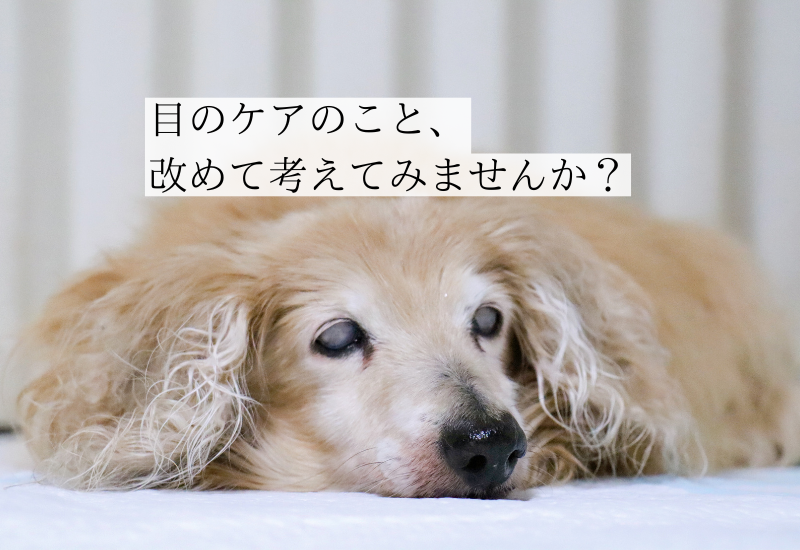
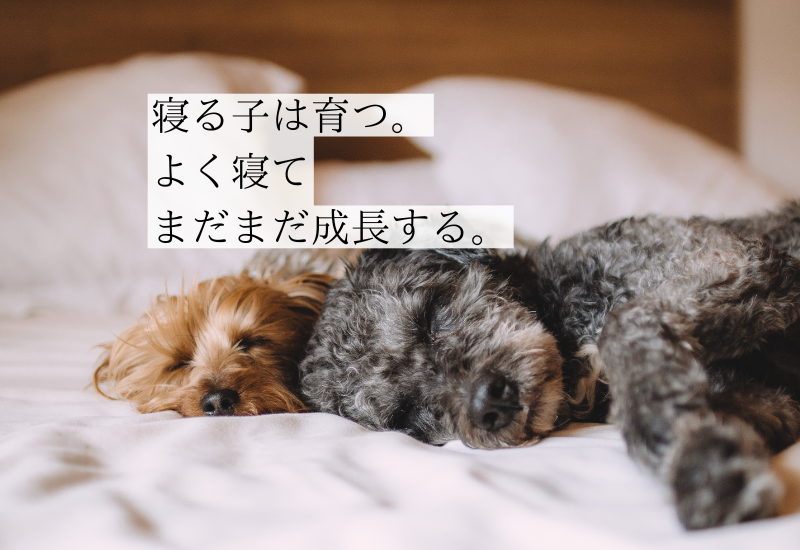




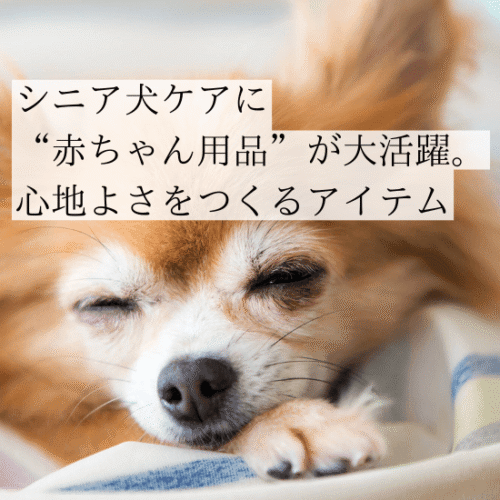
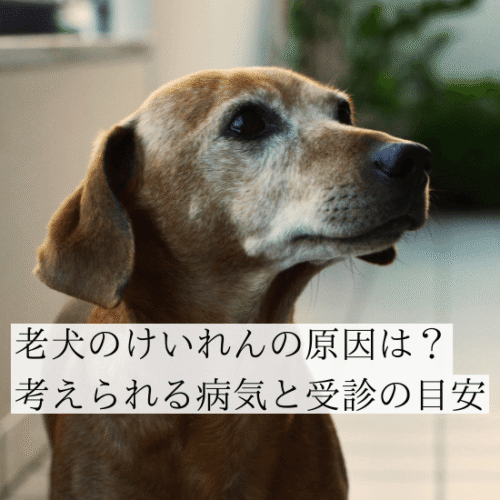
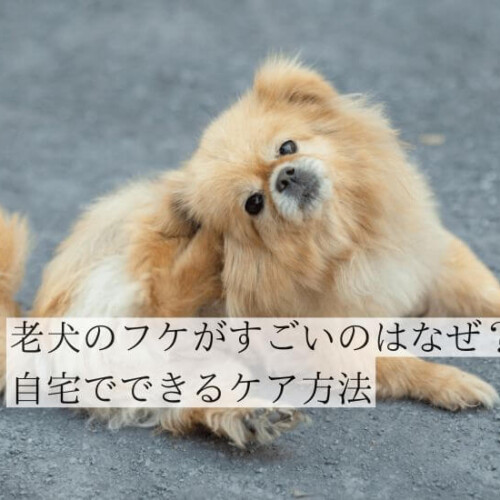

この記事へのコメントはありません。