シニア犬は何歳から?犬種別の目安と老化サイン・フード切り替え時期を徹底解説

「うちの子、もうシニアなのかな?」愛犬と長く暮らしていると、ふとそんな疑問を抱く瞬間がありますよね。
犬の老化スピードは犬種や体格によっても大きく違い、小型犬と大型犬ではシニア期の入り方にも差があります。個体差が大きいからこそ、愛犬に合わせたサポートが必要です。
この記事では、「シニア犬は何歳から?」という目安から、シニア用フードに切り替える時期や健康管理のポイントまでわかりやすく解説しています。
実際に14歳の愛犬と暮らしている犬の管理栄養士の私が解説していますので、ぜひ参考にしてください。
シニア犬は何歳から?明確な定義はないが、目安は犬種や体格で異なる

一般的には、「犬の寿命のおおよそ半分を過ぎた頃」がシニア期の目安となり、チワワやトイプードル、柴犬などの小型犬・中型犬なら7歳頃から、ラブラドールなどの大型犬では5歳頃からシニア期に入ると言われています。
しかし実は、「シニア犬」という言葉に明確な法的定義や医学的な厳密ラインはありません。そのため何歳からがシニア犬と呼べるのかは、犬種や体格、さらには個体差によっても異なります。
シニア犬の目安年齢が犬種・体格で違う理由
.png)
シニア期の目安年齢が犬種や体格によって違う理由は、大型犬ほど成長と老化のスピードが速いという体の仕組みにあります。
大型犬は成犬になるまでの成長期が短く、体を支える関節や臓器への負担も大きいため、若いうちから老化の兆候が見られることが少なくありません。
一方で小型犬は、相対的に寿命が長く老化の進行もゆるやかです。成長が穏やかで代謝も安定しており体への負荷が少ない分、同じ年齢でも元気に過ごす期間が長い傾向があります。
また、体重・代謝・関節への負担などの要因によっても、老化のスピードには個体差が出るものです。たとえば、肥満気味の犬や運動量が少ない犬は、関節や心臓への負担が早期に現れることもあります。
ハイシニア期の高齢犬は、年齢とともに愛しさが増すプラチナドッグ

寿命の「2/3」を超えたあたりを「高齢期(ハイシニア期)」と捉える考え方もあります。
高齢犬も同じ様に年齢は目安にすぎませんが、一般的に10歳以上を高齢犬とすることが多いようです。
高齢犬はより一層シニア特有の様子が見られ、穏やかな毎日を過ごす一方で持病と付き合っている子や介護が必要な子も多くいます。
子犬以上に手がかかるようになることもありますが、その時間がとても大切で愛しく思える時期でもあり、私たちは「プラチナドッグ」と呼んでいます。
シニア犬は、年齢の他にも見た目・行動・性格に変化が出る

「うちの子、そろそろシニアかな?」と感じたとき、年齢だけで判断するのではなく、見た目・行動・性格の変化にも目を向けることが大切です。
犬も人と同じように、年齢を重ねるにつれて少しずつ体や心に変化が現れます。
日々の中で気づける小さなサインを見逃さないことが、健康維持や病気の早期発見のために大切です。
見た目でわかる体の変化(毛・体型・目・歯など)

シニア期の代表的な変化は、毛並みや体型、目の輝き、歯の汚れです。これは被毛の新陳代謝がゆるやかになることや、運動量の低下、涙や唾液量の減少などが影響しています。
| 部位 | 変化 |
| 毛並み | ・顔まわりや口元に白い毛が混じる ・全体的にツヤがなくなる ・被毛の毛の伸び方や密度が変わる など |
| 体型 | ・筋肉量が減り、背中や腰のラインが痩せて見える ・運動量の減少で太りやすくなる など |
| 目 | ・白っぽく濁って見える ・目が乾きやすい など |
| 歯 | ・歯石がつきやすくなる ・口臭が強くなる など |
こうした変化はどれも老化の自然なサインではありますが、定期的なケアやチェックで進行をゆるやかにすることも可能です。
行動や性格の変化(散歩・睡眠・食欲など)
.png)
シニア期に入ると、散歩の量や睡眠時間、食欲にも少しずつ変化が見られるようになります。これは筋力や関節の衰え、持久力や嗅覚、消化吸収能力の低下、認知機能の衰えなどの影響です。
| 行動 | 変化 |
| 散歩 | ・スピードが落ちたり、距離を短くしたがる ・段差や階段を避けるようになる など |
| 睡眠時間 | ・日中に寝る時間が増える ・夜間に落ち着きがなくなる、徘徊する など |
| 食欲 | ・食が細くなる ・食べすぎる ・食の好みにうるさくなる など |
| 性格 | ・穏やかになり落ち着きが増す ・不安や甘えが強くなる など |
こうした変化は単なる老化だけでなく、体調や環境の影響も関係しているため、小さな変化を見逃さず観察することが大切です。
老化サインと病気の初期症状は紙一重

シニア期に見られる変化の中には、加齢による自然な老化現象と、病気の初期症状が紙一重のものが少なくありません。
例えば、「最近あまり食べない」「散歩を嫌がる」「寝てばかりいる」といった行動は、年齢のせいに思えますが、実際には心臓病・関節疾患・内臓の不調が隠れているケースもあります。
また、「目が白っぽくなった」「耳が聞こえにくい」「口臭が強い」などの変化も、単なる老化ではなく白内障・外耳炎・歯周病といった病気のサインの可能性も否定できません。
実際に私の愛犬も、10歳を過ぎたあたりからフードの食いつきが悪くなり、はじめは年齢のせいかと思っていましたが大きな病気が隠れていたことがありました。
●要注意な変化や症状の例
- 食欲が急に落ちた、または異常に食べたがる
- 散歩を嫌がる、歩き方がぎこちない
- 寝ている時間が極端に増えた、夜中に徘徊する
- 体重が急に減った・増えた
- 呼吸が荒い、咳をすることが増えた
- 水をたくさん飲む、尿の量が多い(腎臓やホルモン異常のサイン)
- ぼんやりする、反応が鈍くなった(認知機能の低下の可能性)
こうした変化が数日以上続く、または以前の状態と明らかに違うと感じたときは、早めに動物病院を受診しましょう。
特に、食欲・排泄・呼吸の変化は命に関わる病気の初期症状であることもあります。ママさん・パパさんが、いつもと違う愛犬の小さな変化に気づくことが大切です。
シニア犬用フードは何歳から?一般的には7歳、10歳以上の高齢犬専用フードも

愛犬の年齢に合わせて必要な栄養バランスは変化していくため、一般的にシニア犬となる7歳を過ぎたあたりから、シニア用のフードへ切り替えるべきか検討してみましょう。
シニア用のフードには、以下のような特徴があります。
シニア用フードの特徴
- タンパク質量を適正化
筋肉維持と腎臓への負担に配慮。 - 脂肪が控えめ
運動量低下による肥満を防ぎやすくする。 - 消化吸収に配慮
胃腸の機能低下による下痢や便秘を防ぎやすくする。 - 抗酸化成分を強化
細胞の老化や免疫低下をサポート。 - 関節サポート成分を配合
足腰の健康維持をサポート。 - ナトリウムやリンを調整
心臓や腎臓への負担に配慮してミネラル量をコントロール。
そのほか、噛む力が弱くなったシニア犬でも食べやすいような形状や食感のフードや、嗅覚が衰えても食欲がわくよう、香り立ちを工夫しているフードなどもあります。
もちろん、今与えているフードが愛犬の体質に合っている場合は無理にシニア用に切り替える必要はありません。ですが、年齢が進むにつれて体質や食欲、食べやすさなどの観点から、フードを変更する必要が出てくることが多いです。
またフードメーカーによっては、「11歳から用」「13歳から用」などと、より繊細なシニア期の愛犬に合わせやすいようにしているフードもあります。
愛犬の体調や食欲、体重の変化を見ながら、健康状態に合わせてフードを見直すことが、シニア期を元気に過ごすためのポイントです。
何歳まで一緒にいられる?シニア犬の健康をサポートする4つのポイント

シニア犬と呼ばれる年齢を迎えても、日々の健康管理次第で快適に長生きをサポートすることは可能です。体調や生活リズムに合わせたケアを続けることで、心身ともに充実したシニア期を過ごせるでしょう。
ここでは、シニア犬をサポートするための4つの基本ポイントを紹介します。
①食事管理

加齢とともに代謝や消化機能が低下するため、年齢に合った栄養バランスの食事が欠かせません。ポイントは「量より質」。タンパク質は筋肉や免疫力を維持するために必要ですが、腎臓への負担を考えて良質なたんぱく源を適量に。
脂質は控えめにし、抗酸化成分(ビタミンE、C、ポリフェノールなど)や関節サポート成分を含むフードがおすすめです。
また、嗅覚や味覚が衰えて食欲が落ちる犬には、香りの強い食材やウェットタイプ、ふやかしたドライフードも視野に入れてください。愛犬が必要な量を食べ切れるように与え方や与える回数を適宜見直しましょう。
運動管理

若い頃のように長時間の散歩をする必要はありませんが、短時間でもいいので毎日の散歩は運動量を維持するために必要です。
筋肉や関節を動かすことで、代謝や血流が促進され、肥満や関節硬直を防ぐことにつながります。
ただし、シニア犬は体力の消耗が早いため、坂道や段差を避けたり、ゆっくり歩くなど、愛犬の体調に合わせたペースを守りましょう。
また散歩後の水分補給も忘れないようにしてください。無理をさせないことが大切です。
環境管理
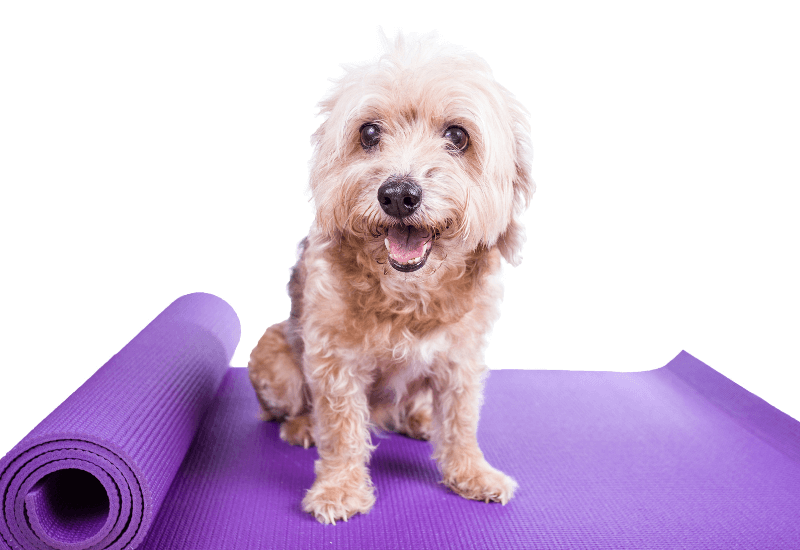
年齢を重ねると、視力や聴力の低下、関節の痛みなどで生活環境がストレス要因になることもあります。愛犬が安心して過ごせるよう、次のような工夫をしてみましょう。
- 床に滑り止めマットを敷く
- 段差の昇り降りをサポートするスロープを設置
- 寝床は温かく、静かな場所に
- 温度や湿度の管理をして、冬の冷え・夏の暑さから守る
こうした小さな配慮が、シニア犬のケガ防止や安眠につながります。
定期的な健康診断

シニア犬の健康診断は、少なくとも半年1回程度が理想です。血液検査や尿検査、エコー検査などを通じて、腎臓・心臓・肝臓などのトラブルを早期に発見できます。
シニア犬では見た目に変化がなくても内臓疾患や腫瘍などが進行しているケースも珍しくありません。日常の観察とあわせて、定期的に動物病院でチェックを受けることが長生きにつながります。
まとめ

「シニア犬」と呼ばれる年齢は、犬種や体格によって異なり、小型犬・中型犬では7歳から、大型犬では5歳からを目安とするのが一般的です。
しかし実際には個体差が大きく、年齢の数字よりも愛犬の見た目や行動、食欲や性格の変化を見てあげることが重要になってきます。
ママさん・パパさんが日々の小さな変化に気づき、愛犬に合う食事を選び、運動や環境の管理を行いましょう。半年に1回程度の健康診断を受けていれば、病気の早期発見もしやすくなります。
年齢を重ねることは、衰えではなく「その子が頑張って生きてきた証」。ゆったりとした歩みの中にも、若い頃にはなかった魅力や絆の深まりが生まれます。
愛犬に寄り添いながら、これからもシニア犬の毎日を笑顔でサポートしてあげましょう。

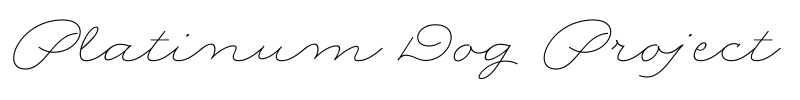

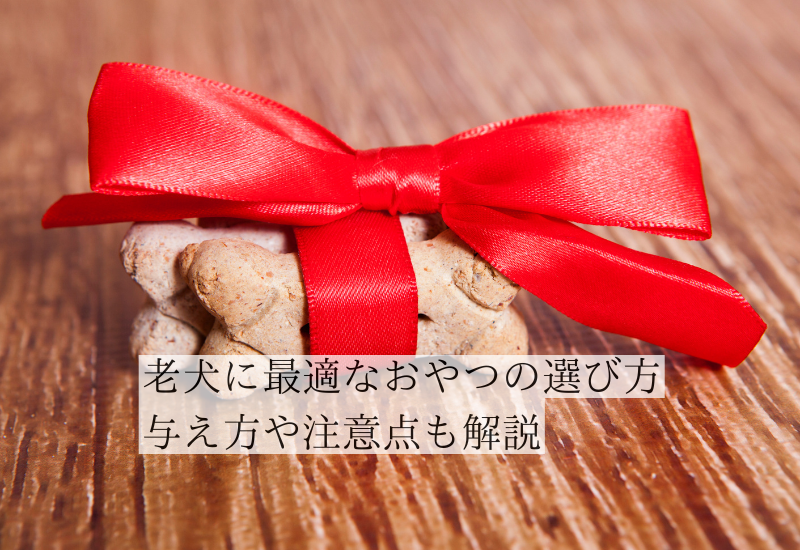










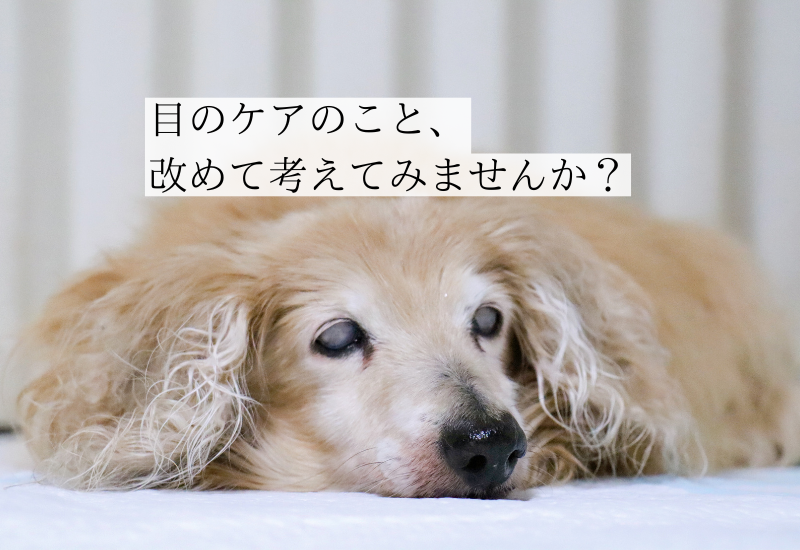
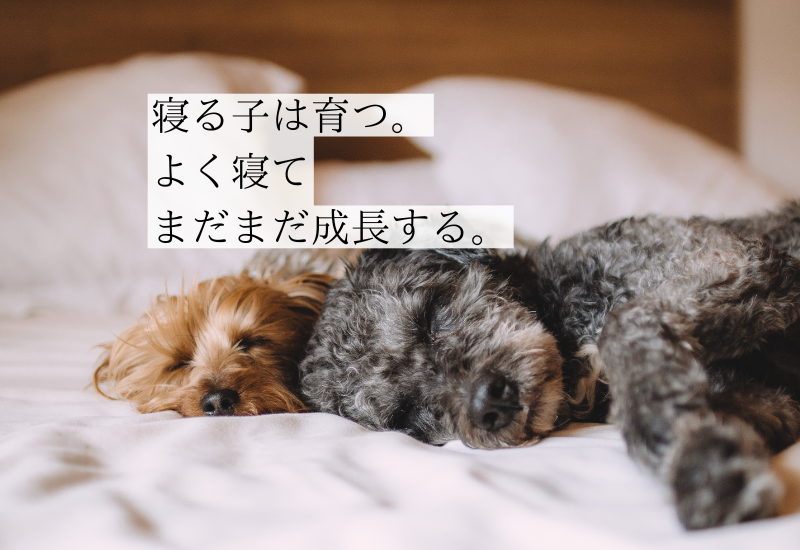








この記事へのコメントはありません。