シニア犬の足がふらつく原因と対処法|無理せず支えるためのケアガイド

「最近、愛犬の足がふらつく気がする……」
そんな変化に気づくと、年齢のせいなのか、病気なのかと不安になりますよね。
シニア犬になると、筋力の低下や関節の衰え、神経のトラブルなど、足がふらつく原因はさまざまです。
なかには早めの受診が必要なケースもあるため、見極めと日常のケアが大切になります。
この記事では、シニア犬の足がふらつく主な原因と、家庭でできるサポート方法を分かりやすく解説します。
「まだ歩けるうちにできること」を知り、愛犬の健やかな毎日を支えていきましょう。
シニア犬の足がふらつく主な原因4つ
.png)
シニア犬の足がふらつく原因は、一つではありません。
老化による筋力の低下から、関節や神経、内臓のトラブルまで、いくつかの要因が重なっていることもあります。
ここでは、よく見られる4つの原因を見ていきましょう。
1.加齢による筋力低下

シニア犬の足がふらつく原因としてもっとも多いのが、加齢による筋力の衰えです。
年齢を重ねると代謝が落ち、散歩や遊びの時間も自然と減っていきます。
そのため、後ろ足の筋肉(特に太ももや腰まわり)が弱くなり、立ち上がるときや歩くときにふらつきが出やすくなるのです。
できるだけ早い段階から、短時間でも毎日の散歩や軽いストレッチを続けることが、筋力維持につながります。
愛犬が床で滑って転んだり、段差を嫌がったりするのも筋力が落ちてバランスを取るのが難しくなっているサインなので、見逃さないようにしましょう。
2.関節や骨のトラブル
.png)
次に多いのが、関節や骨のトラブルです。
代表的なのは、変形性関節症(関節炎)や椎間板ヘルニアがあげられます。
これらは痛みやしびれを伴うことが多く、足をかばうように歩いたり、座り込むことが増えたりすることも。
また、シニア期になると骨の変形や軟骨のすり減りが進みやすくなります。
「散歩の途中で立ち止まる」「後ろ足が上がりにくい」といった変化が見られたら、早めに動物病院での診察を受けましょう。
関節の痛みを放置すると、さらに運動量が減って悪循環になりやすいので気をつけてあげてください。
3.神経や内臓の疾患によるふらつき

シニア犬では、神経や内臓の病気が原因でふらつくケースも少なくありません。
代表的なのが、前庭疾患(ぜんていしっかん)です。
これは耳の奥にある「平衡感覚」をつかさどる部分の異常で、めまいやバランスの崩れを引き起こします。
また、肝臓や腎臓の機能が低下している場合、体に老廃物がたまり、倦怠感やふらつきが出ることもあります。
このように、内臓の不調が足の動きに影響している場合もあるため、見た目だけでは判断できません。
4.爪・肉球・環境によるもの
.png)
意外と見落としがちなのが、環境が原因のふらつきです。
フローリングの床は滑りやすく、シニア犬にとっては転倒のリスクが高くなります。
また、爪が伸びすぎていたり足裏の毛が長くなっていたりすると、しっかり地面をつかめずに滑ってしまうこともあるでしょう。
愛犬が過ごす部屋にはマットやカーペットを敷いたり、こまめに爪や足裏の毛を整えたりするだけで、ふらつきが改善するケースもあります。
シニア犬の足がふらついている時に、動物病院を受診する4つの目安

「少しふらついているだけだから…」と様子を見てしまいがちですが、シニア犬の場合、体の不調が急に進むこともあります。
早めに動物病院を受診することで、治療やケアで改善できるケースも少なくありません。
ここでは、受診を検討すべき主なサインを一つずつ紹介します。
1.ふらつきが続く・悪化している場合

一時的な疲れなら、時間とともに回復することがあります。
しかし、愛犬が数日たってもふらつきが続く・悪化している場合は、病気が関係している可能性を考えましょう。
特に、歩くたびによろける、座り込むことが増える、階段を嫌がるなどの変化が見られたら注意が必要です。
ふらつきが出てからの様子を動画で撮影し、診察時に見せると、獣医師が状態を把握しやすくなります。
2.食欲・元気・排泄に変化がある場合

愛犬の足のふらつきに加えて、食欲不振や元気の低下、排泄の異常がある場合は、体の内部でトラブルが起きているサインかもしれません。
特に、前庭疾患や内臓疾患が原因のときは、ふらつきだけでなく全身の不調を伴うことが多いです。
- ごはんを残す・水をあまり飲まない
- ぼんやりして反応が鈍い
- 便や尿の回数が極端に減った/増えた
上記のような変化があるときは、できるだけ早く受診しましょう。
3.片足だけ・片側だけがふらつく場合

シニア犬が左右どちらかの足だけがふらつく場合は、神経や関節に異常がある可能性があります。
特定の足をかばうように歩いたり、立ち上がるときに片足が上がらなかったりする場合は、椎間板ヘルニアや変形性関節症などの疑いを考えましょう。
シニア犬は、軽い痛みでも無理をすると悪化してしまうことがあるため、早めの診察が安心です。
診察では痛みの部位を確認し、必要に応じてレントゲンや血液検査を行ってくれるでしょう。
4.首のかしげ・眼球の揺れ・回る動きがある場合

もし、首を傾ける・眼球が左右に動く・同じ方向にぐるぐる回るといった動きが見られる場合は、前庭疾患などの神経系トラブルの可能性があります。
この症状は突然あらわれることが多く、見た目はびっくりしますが、早期に治療を始めれば回復するケースもあります。
あわてず、できるだけ早く病院へ連れて行きましょう。受診の際には、以下をメモしておくと診察がスムーズです。
【診察時に伝えたいポイント】
- ふらつきが始まった時期と経過
- どの足(部位)に異変があるか
- 痛がる、震える、ぐったりするなどの様子
- 食欲や排泄の変化
- 服用中の薬やサプリメント
どんな小さな変化でも、獣医師にとっては重要な手がかりになるのでしっかり伝えましょう。
シニア犬の足のふらつき予防:家庭でできるケア&サポート方法3つ
.png)
※前庭疾患の治療を続けて2週間経過した愛犬の写真
シニア犬の足がふらつくようになっても、家庭での工夫次第で快適に過ごせるようになることもあります。
ここでは、日常生活の中で実践できるケアやサポート方法をみていきましょう。
1.滑らない床づくりで転倒を防ぐ
.png)
ふらつきのあるシニア犬にとって、床の滑りやすさは大敵です。
フローリングは、シニア犬にとっては足腰への負担が大きく、転倒や関節の悪化を招くことがあります。
【シニア犬にとっての床づくり対策】
- ペット用の滑り止めマットやカーペットを敷く
- 足裏の毛や爪をこまめにカットする
- 段差や階段にスロープを設置する
特に、寝起きに足をすべらせることが多いシニア犬には、ベッドまわりを重点的に整えると安心です。
2.無理のない運動で筋力を維持する
.png)
シニア犬にとって筋力の衰えを防ぐには、適度な運動が欠かせません。
ただし、若いころのような距離やスピードではなく、シニア犬には“短く・ゆっくり・こまめに”がポイントです。
【シニア犬にとっての運動ポイント】
- 1日1~2回、10〜15分程度の散歩
- 平坦な道を選び、疲れたらすぐに休憩
- 段差の少ない公園などで歩行練習
また、家の中でもできる軽い筋トレとして、支えながら立ち上がる→座る動作を数回繰り返す「立ち座り運動」を取り入れてみるのはどうでしょうか。
シニア犬にとって筋力維持は、ふらつきの改善だけでなく、排泄姿勢の安定にもつながります。
3.介護グッズでシニア犬の“できること”を支える
.png)
最近では、シニア犬の生活を支えるための介護グッズも豊富にあります。
愛犬の足腰が弱っても、自分で歩く時間を増やせるように工夫してあげましょう。
【シニア犬の介護グッズ例】
- 歩行補助ハーネス・ベルト:散歩や立ち上がりをサポート
- 滑り止め靴下:屋内での転倒防止
- 介護マット・クッションベッド:関節への負担を軽減
介護グッズを使用する際は、「できないことを補う」という気持ちではなく、「まだできることを支える」思いで使うのがポイントです。
シニア犬にとって自力で動ける時間が長くなるほど、自信や生活の質(QOL)も保たれるでしょう。
まとめ|シニア犬のふらつきと上手につきあっていこう
.png)
シニア犬の足のふらつきは、年齢を重ねる中で自然と起こる変化のひとつです。
「昔のように戻す」ことよりも、「今の状態を守り、少しでも快適に過ごせるようにする」視点を持つことが大切です。
昨日より少し歩けた、階段を一段登れた、そんな小さな変化を喜べる目線を持つことで、不安よりも「今を一緒に生きている」という安心感が増していくでしょう。

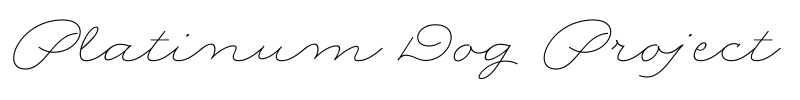


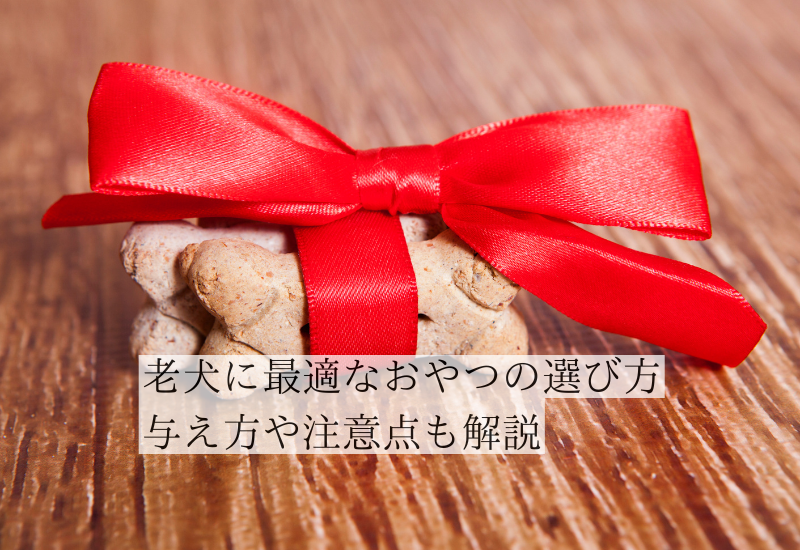


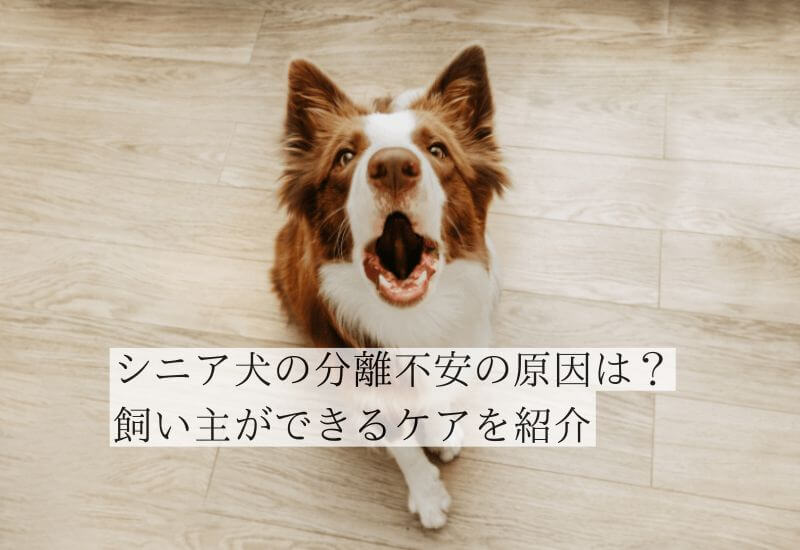








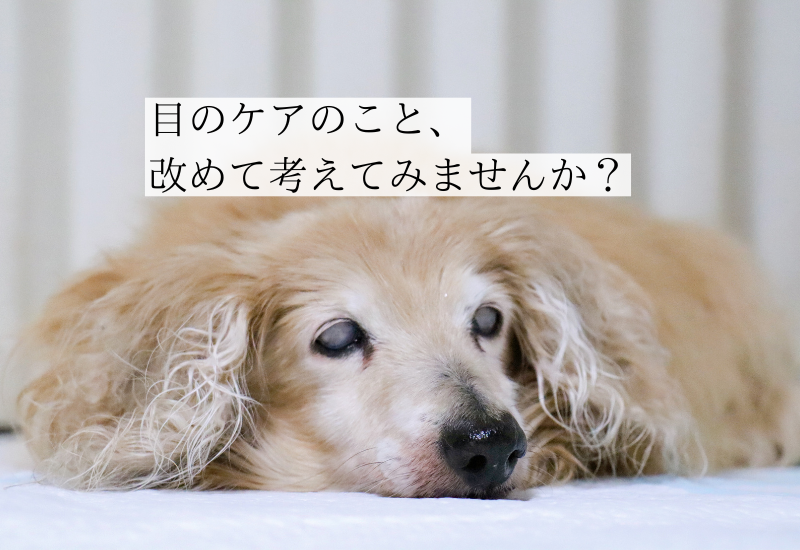
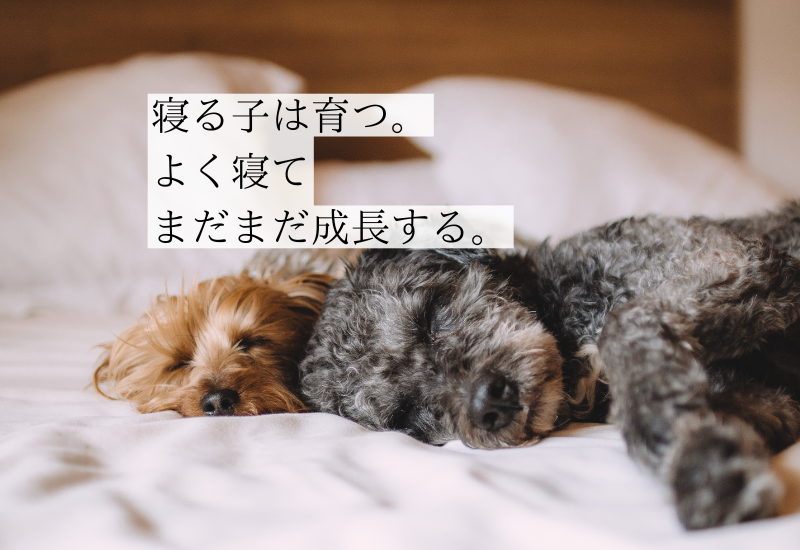





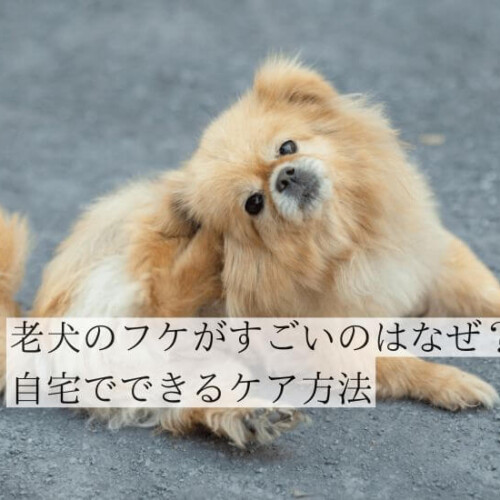
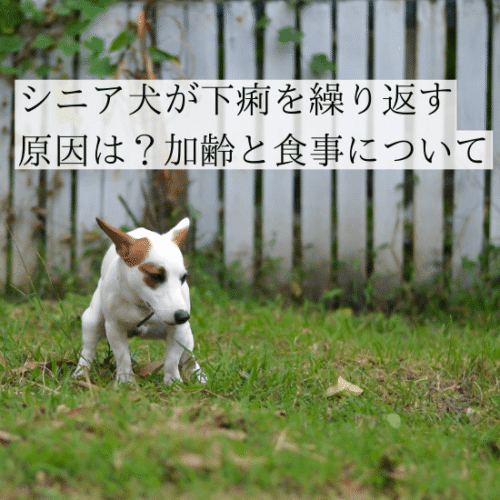

この記事へのコメントはありません。