歩き方が変わったシニア犬は要注意!足腰の異変を見逃さないチェックリスト

歩き方が変わったシニア犬は要注意!足腰の異変を見逃さないチェックリスト
「愛犬の歩き方がぎこちない」「散歩の途中で立ち止まることが増えた」
そんな変化を感じたら、シニア犬からの足もとサインかもしれません。
犬は言葉で不調を伝えることができない分、歩き方・立ち姿・動き方に体調の変化があらわれます。
この変化をそのままにしておくと、関節や筋肉への負担が重なり、痛みが悪化したり、歩くこと自体を嫌がったりすることもあり注意が必要です。
この記事では、シニア犬の歩き方からわかる健康チェックポイントと、早めに気づくための観察方法を紹介します。
日常生活で見えてくるシニア犬の歩き方4つ

シニア犬は筋力の衰えや関節の老化など、少しずつさまざまな変化が出てくるのです。
愛犬がいつもと違う歩き方をしていないか注意深く観察してみましょう。
①歩幅が狭くなった
.png)
愛犬が以前よりも「ちょこちょこ歩き」になっていると感じたら、後ろ足の筋力低下や関節のこわばりが考えられます。
加齢によって、太ももの筋肉(大腿四頭筋)は衰えやすく、体を支える力が弱まると自然に歩幅が小さくなるのです。
とくに、起き上がった直後や寒い日の散歩で顕著に見られることがあります。
ウォーミングアップとして、出発前に軽く体をさすって血行を促すと関節の動きがなめらかになりやすいですよ。
②後ろ足がもつれる・ふらつくようになった
.png)
シニア犬で多いのが「後ろ足のふらつき」です。
段差でつまずいたり、カーペットの端に足を取られたりする場合、神経や関節にトラブルがあるかもしれません。
後ろ足がもつれる原因としては、脊髄の神経の老化、関節炎、股関節形成不全などが考えられます。
また、滑りやすい床環境もふらつきを助長します。
フローリングの上を歩く時間が長いと、滑って踏ん張れず、さらに筋力低下を招く悪循環へとつながるおそれがあります。
シニア犬が過ごす床には、滑り止めマットを敷いたり足裏の毛をカットしてグリップ力を高めたりといった対策が大切です。
③段差を避けるようになった

愛犬が以前は軽々と上がっていたソファや玄関の段差をためらうようになったら、関節や腰に痛みを感じているサインです。
特に小型犬では「膝蓋骨脱臼(パテラ)」、中〜大型犬では「変形性関節症」や「股関節形成不全」などが見られます。
痛みをかばうために、体のバランスを崩してしまうような姿も増えてくるかもしれません。
また段差が多い家庭では、スロープを設置してシニア犬の足腰への負担を軽減してあげましょう。
④歩くスピードがゆっくりになった

「最近、散歩のペースがゆっくりになったな」と感じたら、体力の低下や内臓の不調が隠れていることもあります。
加齢とともに心臓や肺、腎臓の機能が低下すると、運動中に息切れや疲れやすさが目立ってくるのです。
シニア犬の「足もと」で気づく6つのチェックリスト
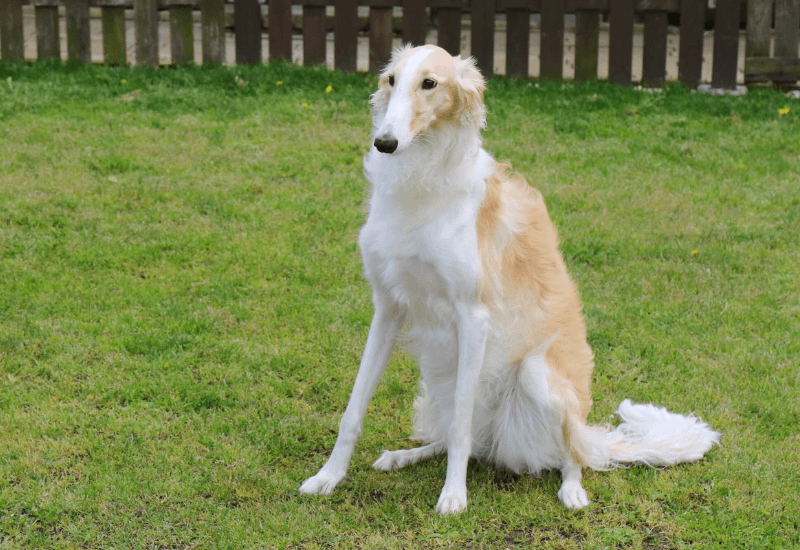
歩き方の変化に加えて、シニア犬の「足もと」をよく観察することで体の異変にいち早く気づけることがあります。
犬は痛みや違和感を隠す傾向があるため、毎日のケアやスキンシップの中でサインを見逃さないことが大切です。
ここでは、シニア犬の「足もと」でチェックしておきたい6つのポイントを紹介します。
①爪がすり減っている
.png)
シニア犬の爪先が極端にすり減っていたり、左右で減り方が違っていませんか?
これは、足をしっかり上げて歩けていないサインです。筋力低下や関節の痛みで足を引きずるように歩くと、爪先が地面とこすれて摩耗してしまいます。
また、爪が長すぎても歩行バランスを崩しやすく、関節や腰への負担が増します。
月に1回を目安に、動物病院やトリミングサロンでカットしてもらうと安心です。
②肉球がカサカサしている
.png)
健康な犬の肉球は、ほどよい弾力としっとり感がありますが、シニア期になると代謝が落ち、肉球の乾燥が進みやすくなります。
カサカサした肉球は、滑りやすく歩行時のグリップ力も低下し、関節に余計な負担をかける原因にもなるため注意が必要です。
犬用の肉球保湿クリームを使ったり、散歩後にぬるま湯で汚れを落として乾燥を防ぐなどのケアが大事です。
③足裏の毛が伸びている

足裏の毛が肉球を覆うほど伸びてしまうと、フローリングで滑りやすくなります。
滑りやすい床は踏ん張る動作が必要となり、関節や腰に負担がかかってしまうのです。
そのため自宅で足裏の毛をカットする場合は、肉球を傷つけないようにハサミの先が丸いタイプを選びましょう。
「滑らない足裏」は、シニア犬にとって安全に歩くための第一歩です。
④足先をよくなめる
.png)
シニア犬が、特に理由が見当たらないのに足先を頻繁になめる場合、痛みや違和感を感じている可能性があります。
関節や爪の根元、肉球のひび割れなどが原因もあるかもしれません。
愛犬が足をなめすぎて赤くなったり、脱毛している場合は早めに動物病院へ連れて行きましょう。
⑤起き上がりに時間がかかる

愛犬が寝起きにスッと立ち上がれず、しばらく体をモゾモゾと動かしているような様子はありませんか?
これは、筋力低下や関節のこわばりのサインです。
シニア犬は加齢とともに関節の可動域が狭まり、動き始めに時間がかかるようになります。
「朝の動きがぎこちない」「後ろ足を引きずる」などの様子が続く場合は、関節炎の初期症状かもしれません。
部屋を冷やしすぎないようにしたり、ベッドをやわらかく保温性のある素材に変えることで関節のこわばりを軽減できることもあります。
⑥お座り姿勢が崩れている
.png)
シニア犬が、きれいに“お座り”ができなくなっている場合も注意しましょう。
お尻が横にずれたり、片足を崩したまま座ったりするようになったら腰や後ろ足のバランスが取りにくくなっているサインです。
長時間のお座りや伏せ姿勢がつらくなると、休息の質も低下します。
愛犬が、体を横にしてリラックスできるようなベッド環境を整えてあげましょう。
早めのケアが大切!シニア犬の足を守る3つのケア

歩き方や足もとに小さな変化を感じたときこそ、早めのケアが大切です。
無理のない範囲で環境を整え、体を支える筋肉や関節を守っていきましょう。
ここでは、今日から実践できるシニア犬の足を守る3つの生活ケアを紹介します。
①滑らない床環境をつくる
.png)
シニア犬の足腰ケアで最も基本となるのが、床環境の見直しです。フローリングは滑りやすく、関節に大きな負担をかけます。
リビングや廊下には、滑り止めマットやカーペットを敷いてあげましょう。
「滑らない床+ケアされた足裏」で、転倒リスクをぐっと減らせます。
②筋力維持のための「ゆる散歩」をする
.png)
加齢による筋力低下は避けられませんが、「歩く」ことで衰えをゆるやかにすることができます。
ただし、若いころのように長時間歩かせるのではなく、短時間×低負担がポイントです。
【ゆる散歩のポイント】
- 1日2回、10〜15分程度の散歩
- 芝生や土の地面など、やわらかい場所を選ぶ
- 気温が低い朝晩の時間帯に行う
散歩の途中で立ち止まることがあっても、焦らず愛犬のペースに合わせてあげましょう。
シニア犬にとって「ゆっくりでも毎日歩くこと」が、筋肉と関節の健康を保つ秘訣です。
③定期的な健康診断を受ける

シニア犬の歩き方の変化や足腰の痛みは、ゆっくりと進行することが多いです。
シニア犬は最低でも半年に1回は動物病院でチェックを受けることで、関節炎や神経系の異常を早期に発見できます。
【動物病院でのチェック項目】
- 関節可動域のチェック
- レントゲン検査
- 血液検査(炎症や筋肉酵素の確認)
「シニア期だから仕方ない」と思ってしまいがちですが、早めのケアで痛みの進行を防げるケースも少なくありません。
シニア犬の定期診断は、長生きのための習慣として取り入れていきましょう。
まとめ|シニア犬にとって家族の目は最高のセンサー
.png)
どんなに良いフードやサプリを使っても、愛犬の体調変化に気づけるのは毎日一緒に過ごしているママさん、パパさんです。
シニア犬の足もとを観察することは、病気の早期発見だけでなく「今の健康を守ること」にもつながります。
愛犬にとってママさん、パパさんの視線こそが一番頼れるセンサーです。その目と手で、シニア犬の毎日を支えてあげましょう。

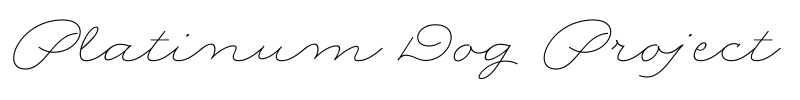


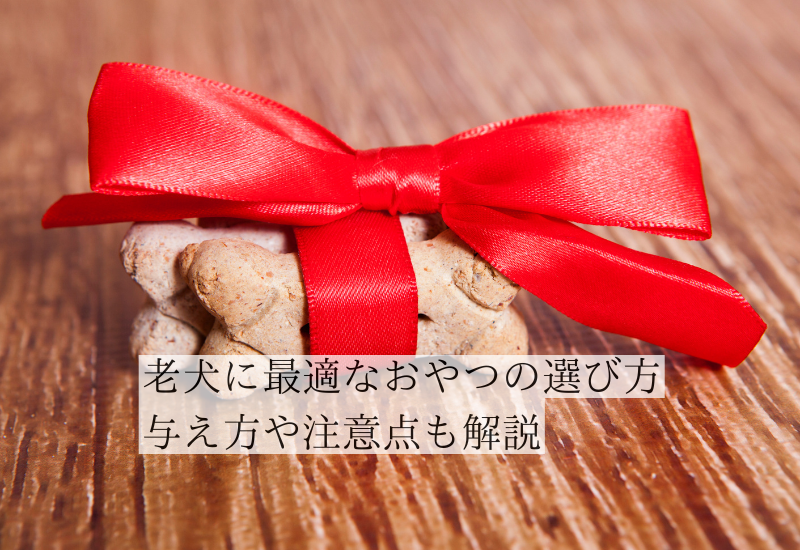



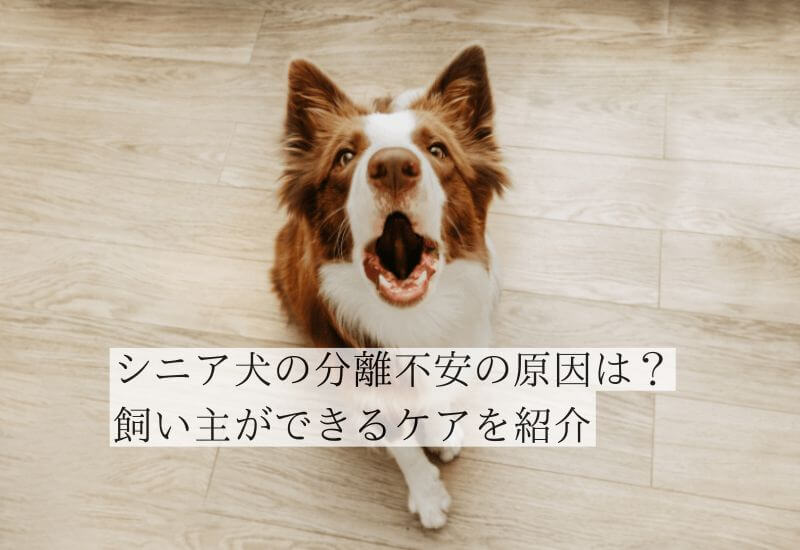







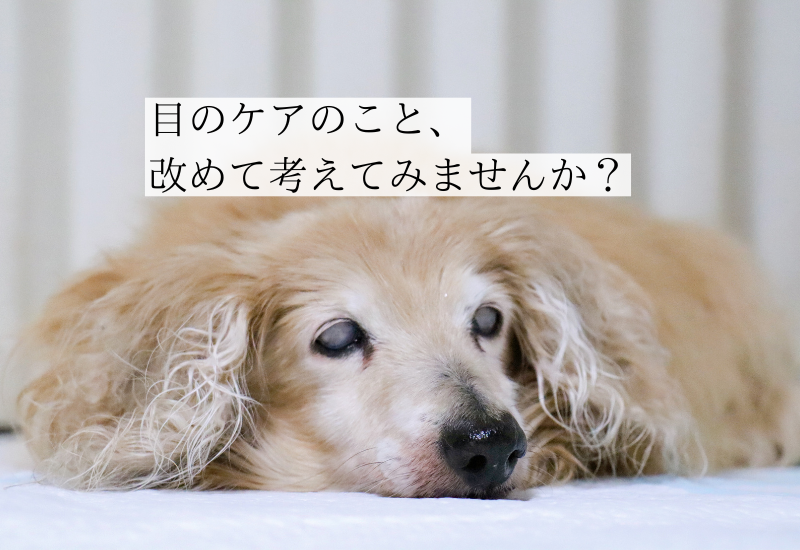
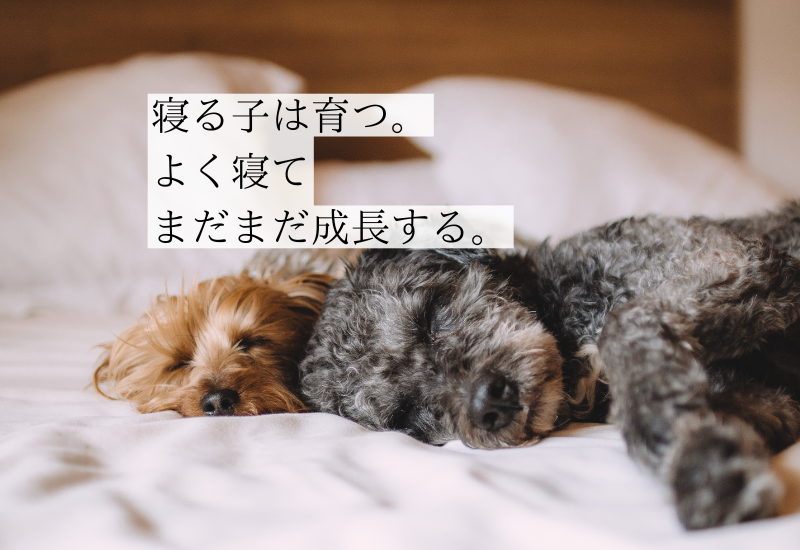
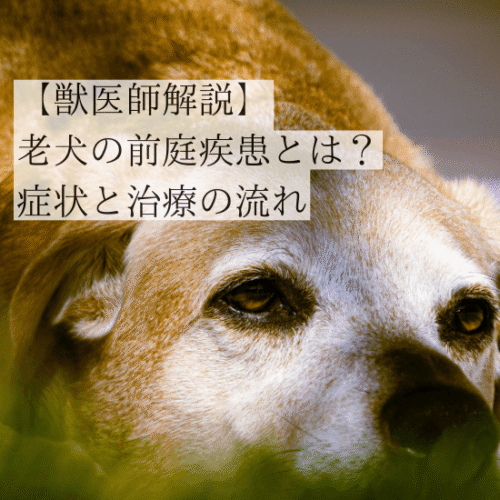





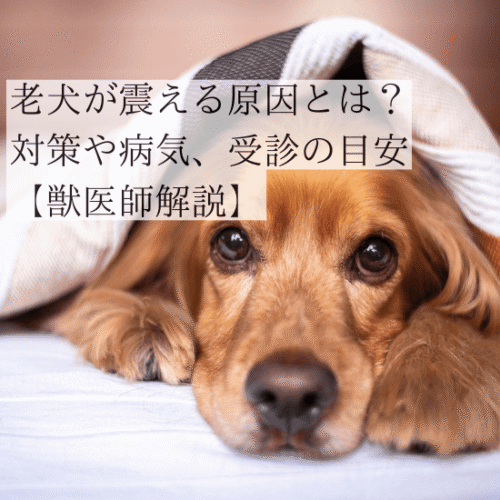

この記事へのコメントはありません。