シニア犬の体重増加の原因3つ|老犬の肥満を解消する食事と運動の方法

シニア期に入った愛犬を抱き上げたとき「ちょっと重くなったかも……」「明らかに体重が増加している」と感じたことはありませんか?
年齢を重ねると、見た目がふっくらすることもありますが、そのわずかな変化が実は重大な健康サインになっている場合もあります。
「年だから仕方ない」と思いがちな体重の増加が、心臓や関節に余分な負担をかけ、将来的に病気を招くこともあるのです。
この記事では、シニア犬が太りやすくなる3つの理由と、健康的に体重を戻すための食事・運動のコツをわかりやすくご紹介します。
愛犬が長く元気に過ごせるよう、今日からできるケアを一緒に見直してみましょう。
シニア犬の体重が増加する原因3つ
.png)
愛犬がシニア期に入ると、体のメカニズムの変化により体重が増加しやすくなります。
また、シニア犬の肥満は単なる見た目ではなく、健康を脅かす問題です。
シニア犬の体重増加は、主に以下の3つの原因が複合的に絡み合っています。
- シニア犬が太る原因1:年齢に伴う基礎代謝の低下
- シニア犬が太る原因2:運動量や活動時間が著しく減少
- シニア犬が太る原因3:ごはんやおやつの量が過剰である
ここで詳しく見ておきましょう。
シニア犬が太る原因1:年齢に伴う基礎代謝の低下
.png)
年齢を重ねると、愛犬の体内でエネルギーを燃やす働き(代謝)がゆるやかになります。
その結果、基礎代謝が低下し、若い頃と同じ食事量ではエネルギー過多になりやすくなるのです。
一般的には、成犬期と比べて大幅にエネルギー要求量が減少すると報告されています。
つまり、以前と同じ食事を与えていても、余ったカロリーが脂肪として蓄積され、体重増加につながるのですね。
特に、食欲が旺盛なシニア犬ほど注意が必要です。「元気だからまだ大丈夫」と思わず、年齢や運動量に合わせたカロリー調整を心がけましょう。
シニア犬が太る原因2:運動量や活動時間が著しく減少
.png)
加齢による骨・関節の違和感や骨格筋の低下から、愛犬は散歩や遊びを嫌がるようになり、結果としてほとんどの時間を寝て過ごすようになります。
この活動レベルの低下は消費カロリーを減らすだけでなく、「サルコペニア(筋肉が減って動きにくくなる状態)」を引き起こし、代謝が二重に低下する悪循環を生みます。
「無理をさせたくない」と運動を控えるのではなく、「負担なく動けるか」を考えることがシニア犬の肥満を防ぐカギです。
シニア犬が太る原因3:ごはんやおやつの量が過剰である
.png)
前の2つの原因に加え、ママさんパパさんの「ついつい与えすぎてしまう」行動もシニア犬が太る大きな要因です。
老犬にねだられて、おやつを与えてしまう方も多いですよね。私も犬と暮らしているので、その気持ちは痛いほどわかります。
しかし、「ほんのひとかけらだけ」と思って与えるおやつや多めの食事は、シニア犬にとって余分なカロリーになっている可能性があるのです。
過剰な食事は生活習慣病や関節疾患のリスクを高め、結果的に寿命を縮めるおそれがあるので注意しましょう。
シニア犬の体重増加は放置しないで!肥満が招く健康リスク

シニア犬が太ると、その影響が体全体に及び、愛犬の健康を深刻に脅かします。
老犬の体が弱っているところに、さらに過度な負荷をかけることになるからです。
ここからは、肥満が招く健康リスクと適正体重の測り方をご紹介します。
体重増加は関節への負担を増やし生活の質を低下させる

過剰な体重は、膝や腰などの関節に慢性的なストレスを与え続けます。この持続的な負荷により、「変形性関節症」や「椎間板ヘルニア」といった疾患が急速に悪化します。
増加した体重1kgあたり、関節には数倍の負荷がかかるため、痛みが増して活動量が減り、さらに肥満が進むという深刻な悪循環を引き起こします。
楽しそうに走り回る愛犬の姿を維持するためにも、体重管理が重要です。
心臓や呼吸器、糖尿病など様々な病気のリスクを高める

シニア犬が太ると内臓にも影響を与えます。
体内に蓄積された内臓脂肪や皮下脂肪は心臓や肺などの重要臓器を圧迫するため、心臓への負担が増し「僧帽弁閉鎖不全症」などの発症・悪化リスクが高まる恐れがあります。
さらに、首回りについた脂肪で気管が狭くなり、呼吸困難や睡眠時無呼吸などのリスクも高まるほか、インスリンの働きが悪くなり糖尿病などの深刻な病気を引き起こす可能性も。
愛犬のフワフワした触り心地が、病気の原因になっている可能性があるのです。
適正体重の測り方とボディコンディションスコア

愛犬の体型チェックは、体重だけでなく「BCS(ボディ・コンディション・スコア)」という指標で確認することが重要です。
これは、見た目と触診で肥満度を判断する方法です。
| BCS | 判定 | 肋骨の触りやすさ | ウエストのくびれ(上から見たとき) | 腹部の吊り上がり(横から見たとき) |
| 1 | 削痩(痩せすぎ) | 脂肪がなく、骨が容易に見えて触れる | 極端な砂時計型 | 顕著に吊り上がっている |
| 2 | 体重不足(痩せ気味) | ごく薄い脂肪に覆われるが、容易に触れる | 顕著な砂時計型 | はっきりと吊り上がっている |
| 3 | 理想的 | 薄い脂肪に覆われるが、容易に触れる | 適度なくびれがある | 腹部の吊り上がりがわずかにある |
| 4 | 体重過剰(太り気味) | 厚い脂肪に覆われ、触るのが難しい | くびれがほとんどない | 腹部の吊り上がりがほぼない |
| 5 | 肥満 | 厚い脂肪に覆われ、触れない | 腰が横に広がり、くびれがない | 地面と並行、または垂れ下がっている |
愛犬の体を触って「肋骨の感触がわかりにくい」と感じたら、それは肥満のサインです。放置せず、今日からできる対策を始めましょう。
シニア犬の体重増加を解消する食事と運動の具体的な方法

シニア犬の体重増加を解消し、愛犬の健康長寿をサポートするためには、「食事」と「運動」の2つの柱での対策が大切です。
ここでは、シニア犬の体型維持に欠かせない食事と運動について解説します。
ポイント1:高タンパク・低カロリー食を選ぶ
.png)
ダイエットの基本は、食事の質と量の見直しです。
まず、ダイエット中の食事は筋肉量を維持するため「高タンパク・低カロリー」を選びましょう。
良質な動物性タンパク質をしっかりと与えつつ、脂肪分や炭水化物(糖質)の摂取を抑えることが必須です。
市販のシニア犬用ダイエットフードを積極的に活用しましょう。
ただし、フードを急に変えると食べなくなる場合があるため、1週間~10日程度の時間をかけて徐々に切り替えることが失敗しないコツです。
ポイント2:おやつを含めたカロリーを正確に計算する

シニア犬が太るのを防ぐには、おやつを含めた総カロリー量の厳密な管理が欠かせません。
実際、おやつが原因でカロリーオーバーになっているケースは非常に多いのです。
おやつを低カロリーのものに置き換えたり、1日の総カロリーの10%以内に収めたりと、厳格にルールを決めましょう。
このルールをご家族全員で共有し、徹底することが何よりも大切です。
ポイント3:無理のない範囲で散歩や遊びを取り入れる

運動は消費カロリーを増やすだけでなく、筋肉の維持やストレス発散にもつながります。
ただし、肥満気味の老犬に急な激しい運動は、関節への負担が大きすぎるためNGです。
散歩は、愛犬のペースを最優先し、距離や時間を調整しましょう。
平坦な道でのゆっくりとした散歩に加え、水泳やドッグプールでの水中運動は、関節に負担をかけずに全身の筋肉を安全に維持できるためおすすめです。
このような優しい変化を加えることで、愛犬の未来は大きく変わります。
消化酵素や関節サポートサプリでシニア犬の体重増加と健康をサポート

食事と運動の見直しに加えて、サプリメントを上手に活用することも、シニア犬が太ることを予防する心強いサポートになります。
ここからは、体重と健康管理に役立つサプリメントの活用法について解説します。
サプリメントで消化機能と関節の働きを助ける
.png)
シニア犬は消化吸収能力が落ちているため、サプリメントでその働きを助けてあげましょう。
代表的なサプリメントは次の通りです。
| サポート目的 | 推奨されるサプリメント成分 | 期待できる変化 |
| 消化吸収の改善 | 消化酵素、乳酸菌 | 栄養を効率よく吸収し、お腹の調子も整い快便に。 |
| 関節の保護 | グルコサミン、コンドロイチン | 関節の炎症を抑え、痛みが減って散歩をより楽しめるように。 |
| 代謝のサポート | L-カルニチンなど | 脂肪の燃焼を助け、より若々しく機敏に動けるようになる。 |
サプリメントはあくまで補助的なものですが、「少しでも楽に」「いつまでも元気に」というママさんパパさんの思いを支える心強い味方です。
愛犬に合ったフードとサプリを動物病院で相談する

ここまで、シニア犬の体重増加への対策をお伝えしましたが、愛犬の健康状態や肥満の原因は、個体によって異なります。
特に持病がある場合や、急に体重が増えた場合は、自己判断せずにプロの意見を聞くことが最も重要です。
大切な愛犬に本当に合ったフードやサプリメント、そして病気の可能性がないかを確認するためにも、まずはかかりつけの動物病院で相談しましょう。
獣医師に相談することで、愛犬の体重管理に対する不安や疑問が解消し、ママさんパパさんの心がスーッと軽くなるでしょう。
愛犬の健康長寿のために、今すぐ行動を起こしましょう。
まとめ|シニア期の入った愛犬の健康長寿は「体重増加の予防」と「適切なサポート」から
.png)
シニア犬の体重増加は、関節炎や心臓病など、愛犬の健康を脅かす深刻なリスクとなります。
【体重増加の主な原因と対策のポイント】
| 原因 | 対策 | 具体的な行動 |
| 代謝低下(必要なエネルギー減少) | 食事の改善 | 「高タンパク・低カロリー食」を選び、おやつを含めたカロリーを厳密に管理する。 |
| 運動量減少(消費カロリー不足) | 運動の継続 | 関節に負担をかけないよう、体力に合わせた散歩や水中運動を無理のない範囲で続ける。 |
| 過剰摂取(与えすぎ) | 家族でルール化 | BCS(体型チェック)で愛犬の適正体重を把握し、家族全員で給与量を守る。 |
愛犬の健康状態やフード選びに迷ったら、自己判断せずにかかりつけの動物病院に相談しましょう。
ママさんパパさんの愛情と正しいケアが、愛犬の元気な毎日を守ります。

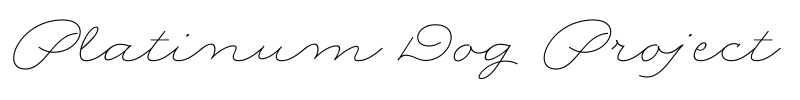

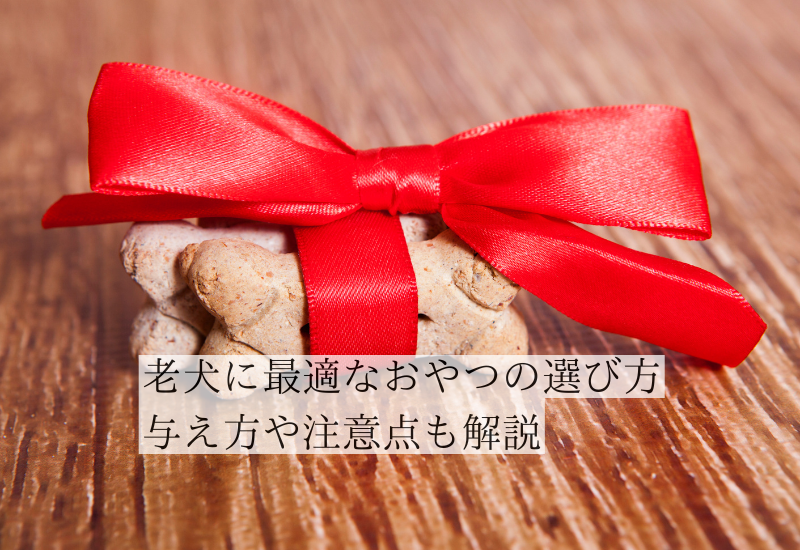










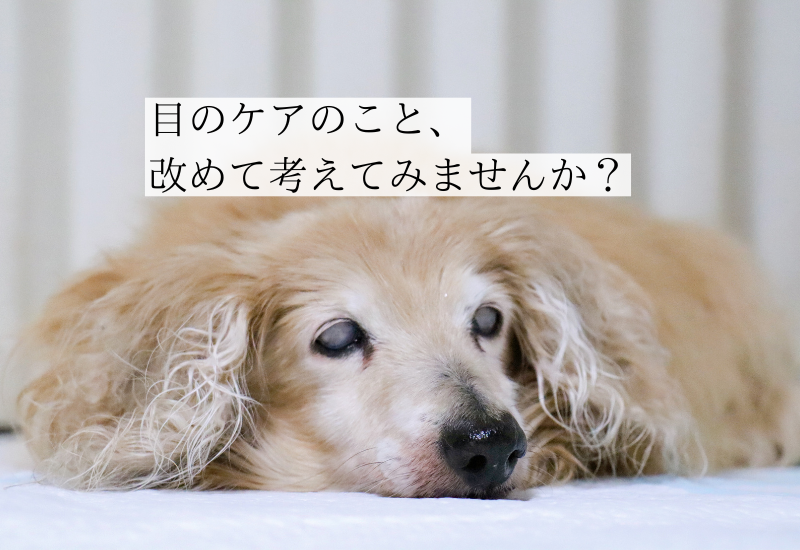
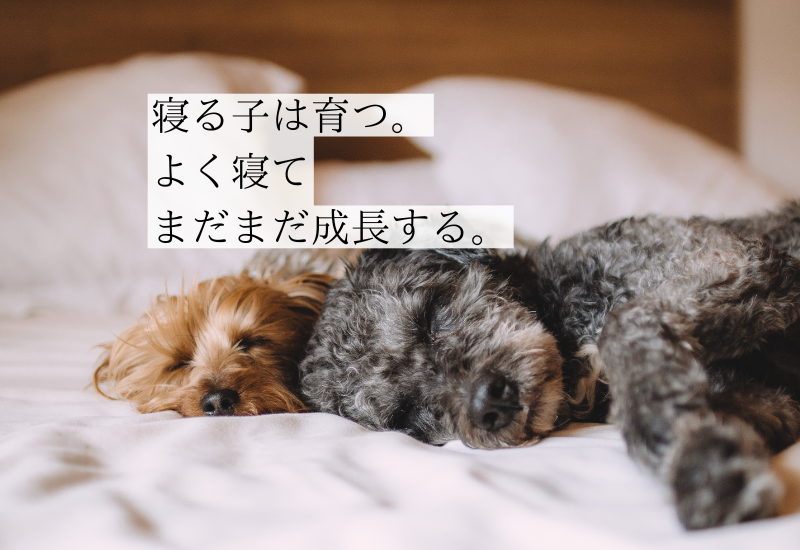


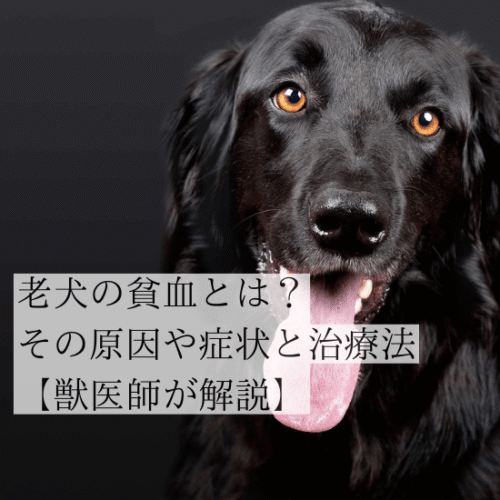
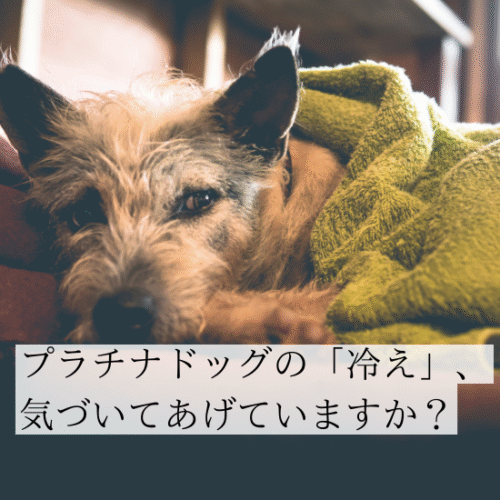




この記事へのコメントはありません。