シニア犬のイボは放置NG!良性・悪性の種類と受診の目安を解説

愛犬が年をとるにつれて、「あれ?こんなところにイボが…」と気づく飼い主さんは少なくありません。
これは老化現象の一部であることも多いですが、放置してはいけないできものである可能性もあります。
私の14歳の愛犬も体のあちこちにイボがあり、良性のイボもあれば悪性の腫瘍もありました。
この記事では、シニア犬にイボが出来やすい理由や、悪性・良性のイボの特徴、病院へ行く目安などを解説しますので、愛犬のイボが不安なときの参考にしてください。
シニア犬にイボができやすい4つの理由

シニア犬は、次の4つの理由から若い頃よりもイボができやすい体質になっています。
- 皮膚のターンオーバー(新陳代謝)の低下
- ホルモンバランスの変化
- 紫外線や摩擦などの外的刺激
- 免疫力の低下
上記のようなイボの原因は、複数の要因が重なって生じることも多いです。それぞれについてわかりやすく解説しますので、シニア期の愛犬について理解を深めましょう。
①皮膚のターンオーバー(新陳代謝)の低下

シニア期になると、皮膚のターンオーバーが低下し、人でいう「老人性のイボ」と呼ばれるイボができます。
皮膚の細胞が新しく生まれ変わるスピードが落ちるため、古い角質や皮脂がうまく排出されにくくなり、皮脂腺や毛包の細胞が過剰に増殖してしまう、という状態です。
②ホルモンバランスの変化

加齢の影響でホルモンの分泌バランスが変化することもシニア期の特徴です。その影響は皮脂の分泌量や毛周期にも及び、皮膚の代謝バランスが乱れてイボが発生しやすくなります。
特に、ホルモンの影響を受けやすい小型犬や中型犬では、このタイプのイボが増える傾向にあるため、皮膚の状態をよく観察しておきましょう。
③紫外線や摩擦などの外的刺激

日光(紫外線)は皮膚細胞のDNAにダメージを与え、長年の蓄積によって細胞の異常増殖を引き起こすことがあります。
また、首輪やハーネス、洋服のこすれなど慢性的な刺激もイボの原因のひとつです。こうした刺激は特に首まわりや背中など、摩擦の多い部位に現れやすい傾向があります。
④免疫力の低下

免疫力が落ちると、ウイルス性のイボができやすくなります。若い犬でも起こりますが、シニア期では免疫細胞の働きが弱まることで再発や多発に注意が必要です。
体調や食生活、ストレスも免疫機能に関わるため、日々のサポートが重要になります。
続いて、実際にどのようなイボが多いのか、良性と悪性にわけて紹介します。
シニア犬に多いイボの例【良性】
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです
シニア犬に見られるイボには、良性腫瘍と呼ばれる命に関わる心配のないできものも多いです。
ただし、良性であっても場所や大きさによっては生活に支障をきたしたり、愛犬が気にして掻いてしまえば、出血して感染することもあります。
良性のイボでも治療が必要になるケースもあることはきちんと覚えておきましょう。シニア犬によく見られる代表的な良性のイボは以下の通りです。
皮脂腺腫

シニア犬の皮膚に最も多く見られる良性腫瘍のひとつです。
皮脂を分泌する「皮脂腺」の細胞が過剰に増殖してできるもので、特に10歳以上の高齢犬でよく見られます。
- 見た目
丸く盛り上がったイボ状。色は肌色〜薄茶色。 - 触感
やや硬く、表面がざらざらしていることも。 - できやすい場所
顔、頭、まぶた、首まわり、背中など。
皮脂腺腫は良性で転移の心配はほぼありません。
ただし、愛犬が掻いたり舐めたりして出血・化膿することがあるため、気にしている場合はイボを保護したり、エリザベスカラーで刺激を防ぐことが大切です。
また、イボが急に大きくなったり黒く変色した場合は、悪性の可能性もあるため動物病院で1度検査を受けましょう。
皮膚乳頭腫

いわゆるウイルス性のイボです。
犬パピローマウイルスの感染によってでき、若い犬にも見られますが、免疫力が落ちるシニア犬では再発や多発が起こりやすくなります。
- 見た目
カリフラワーのような形で、細かくデコボコしている。 - 色
薄いピンク〜白っぽい色。 - できやすい場所
口のまわり、まぶた、足先など。
通常は良性で自然に小さくなることもありますが、免疫力が低下している犬では広がることがあります。
ウイルス感染が関係しているため、他の犬との接触は避け、清潔を保つことが大切です。
表皮嚢胞

皮膚の下に袋状の構造(嚢胞)ができ、そこに角質や皮脂がたまるタイプの良性イボです。
「粉瘤(ふんりゅう)」とも呼ばれ、毛穴の詰まりや皮膚の傷が原因で起こります。
- 見た目
丸く膨らんだしこり。中央に黒い点があることも。 - 触感
やや柔らかく、押すと中身が動くような感触。 - 特徴
破裂すると白や黄ばみのある膿のような物質が出て、におうことがある。
中身を無理に押し出すと感染や炎症の原因になるため、破裂した場合は動物病院で処置してもらいましょう。
脂肪腫

中高齢の犬でよく見られる、脂肪細胞が増えてできる良性腫瘍です。肥満とは関係なく、痩せた犬にもできます。
- 見た目
皮膚の下にできる柔らかいしこり。皮膚表面は変化なし。 - 触感
ぷにぷにと弾力があり、動かすと少しずれる感じ。 - できやすい場所
体幹部、脇腹、太もも、お腹まわりなど。
脂肪腫は良性ですが、大きくなると歩行や関節の動きを妨げることがあるため、獣医師と相談のうえ手術で切除することもあります。逆に、場所や大きさによっては経過観察で済むケースも多いです。
このように、シニア犬のイボに良性のもの多くあります。
しかし、「見た目が変わった」「急に大きくなった」「出血した」といった変化が見られた場合は、悪性腫瘍の可能性も否定できません。1度は動物病院で診察を受けましょう。
シニア犬に多いイボの例【悪性】

※画像はイメージです
シニア犬の皮膚にできるイボの中には、悪性腫瘍がイボのように見えるものもあります。
見た目が良性のものと似ているため、飼い主さんが判断するのは難しく、「ただのイボ」と思っているうちに進行してしまうケースも少なくありません。
ここでは、シニア犬に多く見られる悪性のイボを紹介します。
扁平上皮がん

皮膚の表面を覆う細胞ががん化して起こる、皮膚がんの一種です。
紫外線の影響を受けやすく、長年の光ダメージが原因になることもあります。
- 見た目
表面が赤くただれたように見える、またはかさぶたのような盛り上がり。 - できやすい場所
鼻、耳、口まわり、腹部など毛が薄い部分。 - 特徴
初期は小さな傷やイボのようだが、次第に崩れたり出血したりする。
進行すると皮膚の奥深くまで浸潤し、リンパ節や肺などに転移することもあります。早期発見・切除が重要な腫瘍です。
口腔内にできることもあるため、フードを食べづらそうにしていたり、食いつきが悪くなったことが発見のサインになることもあります。
基底細胞腫

皮膚の奥の「基底細胞」から発生する腫瘍で、良性から悪性の中間(境界型)といわれています。
見た目が皮脂腺腫などの良性イボと似ており、区別が難しい腫瘍です。
- 見た目
黒っぽい、または濃い茶色のしこり。つるんとした球状。 - 触感
やや硬く、ゆっくり大きくなる。 - できやすい場所
顔まわり、首、背中。
良性のことが多いですが、まれに悪性化して周囲の組織に浸潤することもあります。手術で完全に切除すれば再発は少ないとされています。
メラノーマ(悪性黒色腫)

メラニンを作る「メラノサイト」ががん化したもので、犬の皮膚がんの中でも特に悪性度が高い腫瘍です。
黒いホクロやイボのように見えることから、発見が遅れることがあります。
- 見た目
黒〜茶色のしこり、または黒いシミのような斑点。 - できやすい場所
口の中、唇、歯ぐき、爪の根元、足先など。 - 特徴
短期間で大きくなる、出血する、潰瘍を伴う。
メラノーマは転移率が非常に高く、肺やリンパ節、骨などに広がることがあります。口腔内にできるタイプは特に悪性度が高く、早期発見と治療が鍵です。
皮脂腺癌

良性の皮脂腺腫とよく似た外見をしており、見た目だけでは区別が難しい腫瘍です。皮脂腺の細胞ががん化して発生します。
- 見た目
肌色〜褐色のイボ状で、表面が崩れやすい。 - 特徴
短期間で大きくなる、出血・ただれを伴う。 - できやすい場所
首、背中、まぶた、体幹など。
転移はまれですが、再発しやすいため外科的切除後も定期的な経過観察が必要です。
肥満細胞腫

犬に非常に多い悪性腫瘍で、見た目がイボや虫刺されにそっくりです。悪性度の幅が広く、外見からは判断できません。
- 見た目
丸く盛り上がったしこり。赤みやかゆみを伴うことも。 - 触感
柔らかいものから硬いものまでさまざま。 - 特徴
大きくなったり小さくなったりを繰り返す。 - できやすい場所
体幹部、脚、顔など。
肥満細胞腫は、体内でヒスタミンなどの物質を放出し、かゆみや腫れ、胃腸症状を引き起こすこともあります。悪性度の判定には細胞診・組織検査が欠かせません。
このように、悪性のイボは良性と区別がつきにくいものが多いです。獣医師でも見た目だけで悪性か良性かを診断することはできず、細胞診や組織生検してイボの性質を診断します。そのため、飼い主さんが自己判断することは絶対にやめましょう。
シニア犬のイボで動物病院を受診する目安

シニア期の愛犬にイボができたら、日々状態を観察し、次のような変化が見られたら病院を受診しましょう。
- 数週間〜1ヶ月ほどの間に急に大きくなった
悪性腫瘍は、良性に比べて細胞分裂のスピードが速く、短期間で急に成長する傾向がある。 - 出血・膿が出る・かさぶたがある
悪性化や感染を起こしている可能性がある。 - 愛犬が気にして掻く・舐める
状態を悪化させたり生活の質を下げる可能性がある。 - 硬さや形が変わった
腫瘍が内部で性質を変えている可能性がある。 - 数が急に増えた
皮膚全体に影響を与える病変や、免疫力低下による腫瘍形成の可能性がある。
ちなみに、イボを見つけた時点で日付と場所、サイズをメモしておくと変化がわかりやすく、受診の際も診断に役立ちます。
また、毎日イボを同じ角度・同じ距離で撮影し、数日~1週間おきに記録しておくと成長スピードを判断しやすくなります。
撮影時に定規やコインを横に置いたり、柔らかいメジャーで直径を測るのもおすすめです。
動物病院を受診した際に、そういった情報を提供することで診察がスムーズにいきやすくなります。
シニア犬のイボが破裂して出血!自宅でできる対処法

シニア犬のイボは、擦れたり、犬自身が掻いたり舐めたりすることで破裂して出血することがあります。
しかし、イボが破裂した場合、自宅で完全に処置することはできません。
基本的には、できるだけ早く動物病院の受診が必要ですが、自宅でできる最低限の対処法とやってはいけないことをまとめました。
自宅でできる対処法
- 清潔なガーゼでやさしく圧迫止血する
・強く押しすぎず、数分間軽く当てて様子を見る。
・ティッシュは傷口にくっつくため避ける。 - 水道水またはぬるま湯で汚れを洗い流す
・血や膿がついている場合は、刺激の少ない水で軽く洗う。
・消毒液は使わない。痛みや刺激で悪化する可能性がある。 - 舐めないように保護する
・エリザベスカラーや洋服で保護し、再出血を防ぐ。
上記のような対応をしたら、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。
くれぐれも、自分でハサミやピンセットを使ってイボを取ろうとしたり、市販の人間用の薬(消毒薬・軟膏など)を塗ることはしないでください。
また、出血しているのに放置することも、感染や炎症を悪化させる原因となるため危険です。
まとめ。シニア犬のイボは「放置しない」が鉄則
.png)
シニア期になると、皮脂腺の働きや免疫バランスの変化により、イボやしこりができやすくなります。
良性で命に関わらないものも多いですが、中には悪性腫瘍が隠れていることもあるため、放置せずに早めに動物病院で確認することが大切です。
また、良性の場合でも日々観察をしておくと、変化があったときにすぐに対応できます。毎日のスキンシップの中で小さな変化を見逃さないようにしましょう。

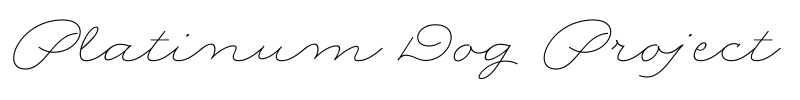


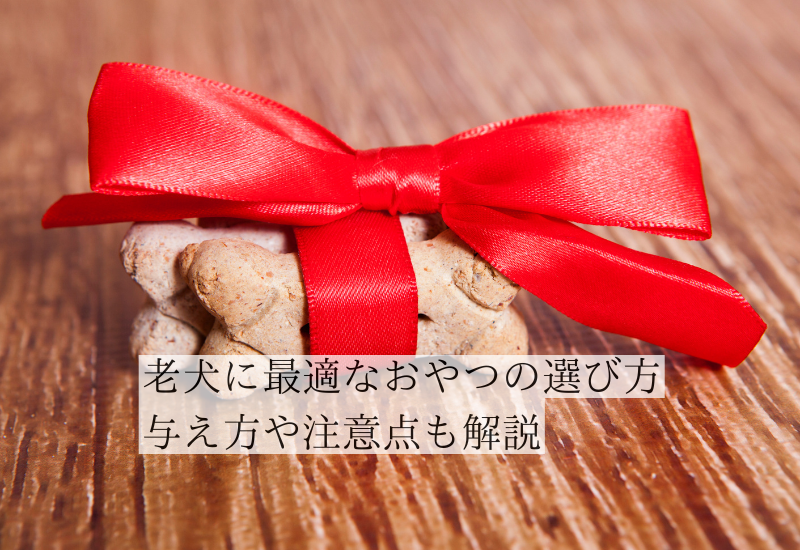


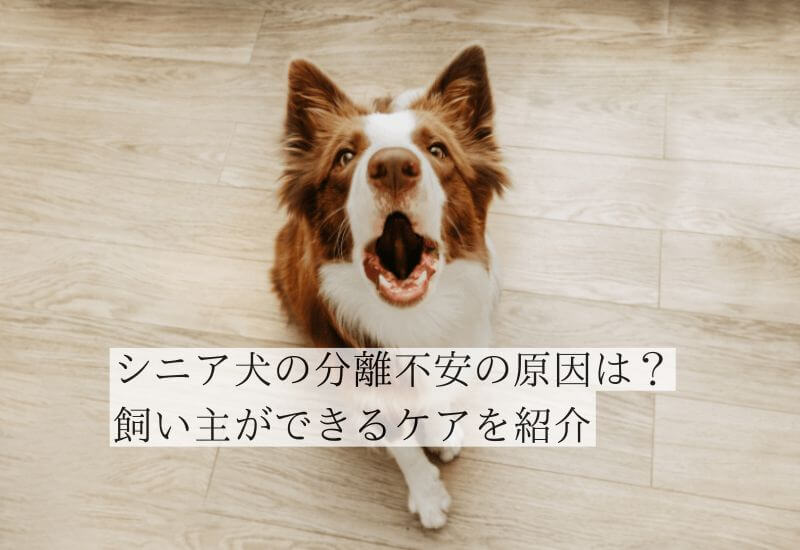








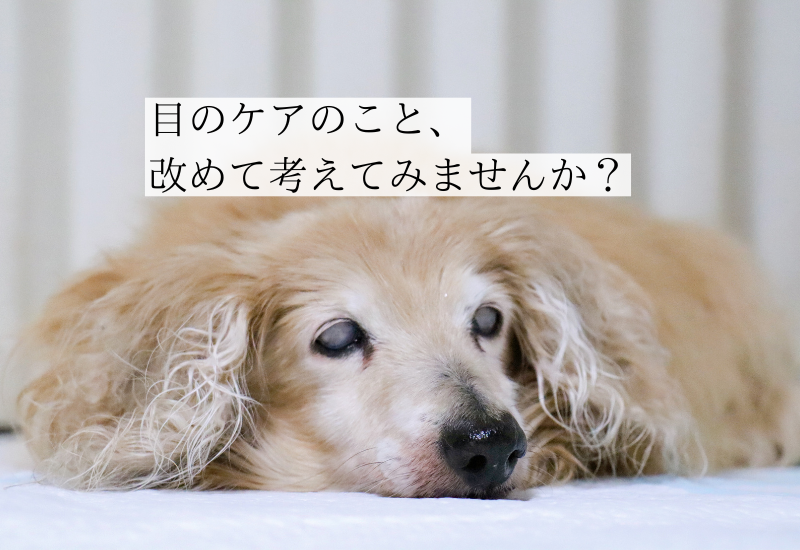
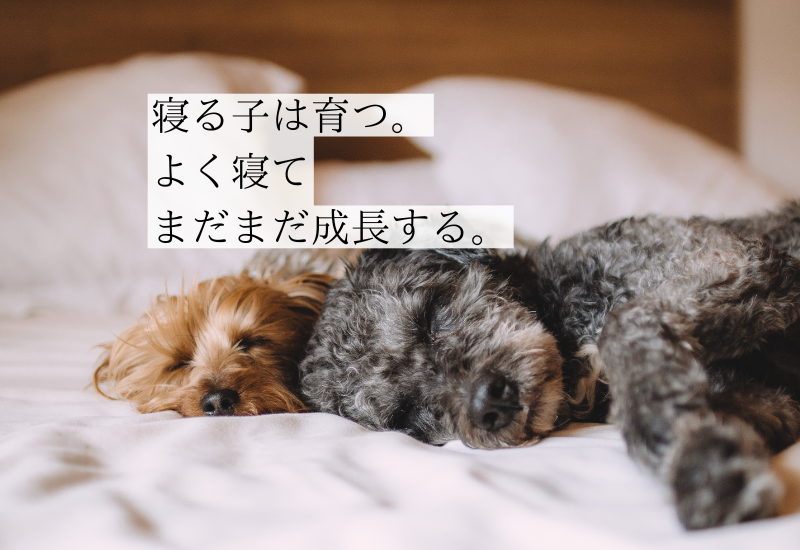



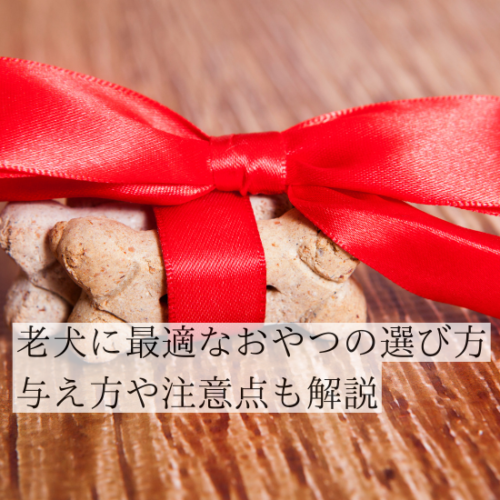




この記事へのコメントはありません。