シニア犬の寝たきり介護、何から始める?環境づくりとケアの基本を解説

「うちの愛犬、寝ている時間が長くなっているけれど…もしかしてこのまま寝たきりになるの?」
シニア期に入ると、少しずつ体の変化が現れてきます。
特に、関節や筋肉の衰えによって自力で立ち上がれなくなると、介護が必要な“寝たきり”の状態になることもあるでしょう。
突然の変化に、「何から始めればいいの?」「うまくお世話できるだろうか」と不安になるママさん、パパさんも多いのではないでしょうか。
もし愛犬が寝たきりになっても、環境を整え、適切なケアを行えば快適に過ごすことは可能です。
この記事では、寝たきりになった愛犬の介護をしていた私がシニア犬の寝たきり介護を始めるときに知っておきたい環境づくりとケアの基本をやさしく解説します。
シニア犬が寝たきりになる主な原因4つ
.png)
シニア犬が寝たきりになる原因は、老化だけではありません。
病気やケガ、生活環境の影響など、いくつかの要因が重なって起こるケースがほとんどです。シニア犬になると体力低下や免疫の低下などによって病気のリスクが高くなります。
ここでは、代表的な原因を一つずつ確認しておきましょう。
1. 関節や筋肉の衰え

シニア犬は年齢を重ねると筋力が低下し、関節の動きも硬くなります。
特に、後ろ足の踏ん張りが効かなくなると立ち上がるのが難しくなり、転倒やふらつきを繰り返すうちに、寝たきりになることもあります。
2. 関節炎や椎間板ヘルニアなどの疾患

シニア犬は関節炎、変形性関節症、椎間板ヘルニアなどの慢性的な痛みを伴う病気になると、動くこと自体を嫌がるようになります。
痛みをかばうことでますます筋力が落ち、寝たきりへと進行してしまうこともあるでしょう。
3. 神経系のトラブル

脊髄や神経の障害によって、足の感覚が鈍くなったり、思うように体を動かせなくなったりする場合もあります。
【代表的な神経系の病気】
- 変性性脊髄症(DM)
…後ろ足から徐々に麻痺が進行し、最終的には歩行困難になる病気。 - 椎間板ヘルニア
…椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで痛みや麻痺を引き起こす病気。 - 脊髄腫瘍
…脊髄内外にできる腫瘍が神経を圧迫し、運動機能の低下や麻痺を引き起こす病気。 - 末梢神経障害
…糖尿病や外傷、加齢などが原因で神経伝達がうまくいかなくなる病気。
特に大型のシニア犬は、神経系の疾患が進行すると自力で立てなくなることがあるので注意が必要です。
4. 病後・手術後の安静期間の影響

人間と同じようにシニア犬も大きな病気や手術のあとは、安静が必要になります。
しかし長期間動かない状態が続くと、筋力が急激に低下し、結果として寝たきりに近い状態になることがあるのです。
寝たきりのシニア犬が安心して過ごせる環境づくりのポイント4つ
.png)
寝たきりのシニア犬を介護するとき、まず整えたいのが家の中の「環境」です。
シニア犬は体が自由に動かせなくなると、ちょっとした段差や温度差が大きな負担になります。
ママさん、パパさんが少し工夫するだけで、愛犬の快適さも介護のしやすさもぐっと変わってくるでしょう。
1.寝床は「清潔・柔らかく・通気性」よくする
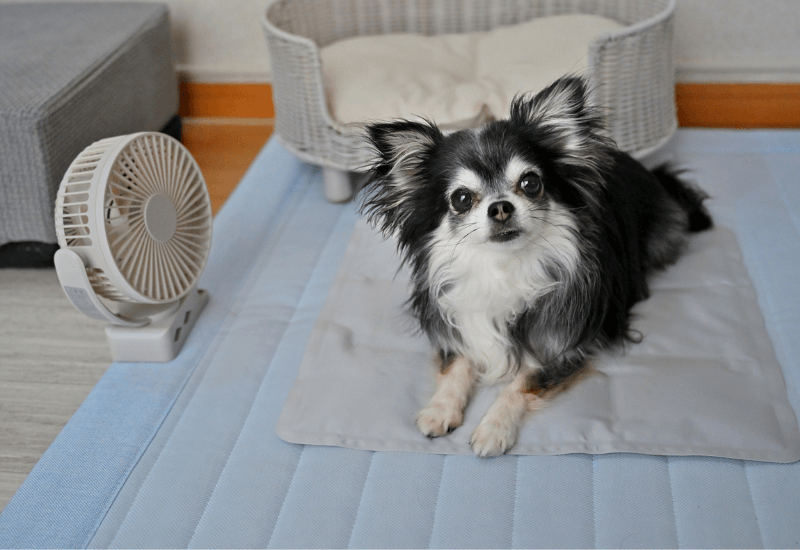
寝たきりのシニア犬は、長時間同じ姿勢でいるため床ずれ(褥瘡)が起こりやすくなります。
そのため、体をやさしく支える低反発マットや介護用ベッドを用意しましょう。通気性がよい素材を選ぶと蒸れにくく、皮膚トラブルの予防にもつながります。
また、寝床には防水シート+吸収パッドを重ねておくと、おしっこ漏れにも安心です。汚れたらすぐに交換し、清潔な状態を保つことは欠かせないですね。
2.段差をなくして安全に移動できるようにする

シニア犬が寝たきりになる前後は、筋力が弱まり、少しの段差でも転倒の原因になります。
リビングや寝室の入口などにある小さな段差はスロープやカーペットでカバーして段差がなくなるようにしましょう。
フローリングの滑りも関節に負担をかけるため、滑り止めマットを敷くのがおすすめです。
部屋の環境を安全に保つことで、「寝たきりになる前の自立した時間」を長く維持することにもつながります。
3.温度・湿度の管理で体調を守る

寝たきりのシニア犬は、自分で体温を調整するのが難しくなります。
室温は25℃前後を目安に保ちましょう。また、愛犬にエアコンの風が直接当たらない位置にベッドを置くこともポイントです。
部屋の中が乾燥しすぎると皮膚トラブルの原因になり、湿気が多いとカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
また、シニア犬にとって湿度が高いと心臓に負担もかかるので湿度管理も大事です。
加湿器や除湿機を使って湿度40〜60%を目安に調整してあげましょう。
4.家族の“手が届く距離”に寝床を用意する
.png)
寝たきり介護は、世話のしやすさ=続けやすさにつながります。
特にシニア犬は、体調が急に変化することもあるためすぐに対応できる距離感を保つことが大切です。
シニア犬の寝床は、ママさん、パパさんが声をかけやすく、様子を見守れる場所に設置するのがポイント。
家族の気配を感じられる場所にいることで、愛犬の孤独や不安もやわらぐでしょう。
寝たきりシニア犬の基本ケア:食事・排泄・体位変換のコツ
.png)
寝たきりのシニア犬を介護するとき、「何から始めればいいの?」と迷うママさん、パパさんは多いでしょう。
まずは、毎日の食事・排泄・体位変換といった基本ケアから丁寧に整えていくことが大切です。
ここでは、無理なく続けられる方法を紹介します。
①食事:姿勢と消化を意識する
.png)
寝たきりのシニア犬は、飲み込みや消化に時間がかかることがあります。
食事の際は少し体を起こして、首が自然な角度になる姿勢をサポートしてあげましょう。
ペット用のクッションやタオルを利用すると安定しやすく、誤嚥(ごえん)の予防にもつながります。
また、フードは消化の良いもの・やわらかいものを選ぶと食べやすさや消化に配慮してあげられます。
動物病院で相談しながら、シニア犬用の療法食やふやかしたフードを与えるのもおすすめです。
なお、水分が不足すると便秘や泌尿器トラブルの原因にもなるため、水分補給も忘れずにしてあげましょう。
② 排泄:清潔を保ち、皮膚トラブルを防ぐ

寝たきりになると、自力でトイレに行くことが難しくなります。そのため、おむつやペットシーツのこまめな交換が欠かせません。
尿や便が皮膚に触れたままだと、すぐにかぶれやただれが起きてしまうため、排泄後はやさしく拭き取り、しっかり乾かすようにしましょう。
おしり周りの毛を短くカットしておくと、汚れがつきにくくお手入れも楽になるのでおすすめです。
また、長時間同じ姿勢でいると血流が滞り、床ずれができやすくなります。
排泄のたびに軽く体勢を変える習慣をつけると、褥瘡(じゅくそう)予防にも効果的です。
③ 体位変換:2〜3時間おきを目安に行う
.png)
寝たきりのシニア犬の介護では、体位変換(姿勢を変えること)がとても大切です。
同じ場所に体重がかかり続けると、血流が悪くなり、皮膚が赤くただれてしまいます。
2〜3時間おきを目安に、右・左・仰向けと体の向きを変えてあげましょう。
体を動かすときは、愛犬の関節や腰に負担をかけないよう、両手でゆっくり支えるのがポイントです。
もし動かすのを嫌がる場合は、クッションやタオルを使って少しずつ角度を変えるだけでもいいでしょう。
寝たきりシニア犬の介護を無理なく続けるため工夫2つ

寝たきりのシニア犬の介護は、決して楽なものではありません。
長期にわたるケアの中で、飼い主自身の心と体が疲れてしまうこともあります。
シニア犬と一緒に暮らしていた私も何度となく、気持ちが落ちてしまうことがありました。
愛犬もママさん、パパさんも穏やかに過ごせるよう、無理なく続けるための工夫を紹介します。
①介護の時間と自分の時間を分ける
.png)
まずは介護の時間と自分の時間を分けることがポイントです。
「しっかり見てあげなきゃ」と気を張り続けていると、知らず知らずのうちにストレスが溜まります。
タイマーを使ってケアの時間を決める、好きな音楽を聴きながら介護するなど、小さなリズムを作ることで気持ちが少し軽くなるでしょう。
またペットカメラを設置しておくと、外出中でも様子を確認できるので安心です。
お世話の方法を省エネ化・効率化することも、介護を長く続けるための大切な工夫と言えます。
②専門家の力を借りる

寝たきりのシニア犬の介護では、獣医師や動物看護師、トリマーなど専門家のサポートを活用するのも重要です。
定期的な健康チェックや体重管理を受けることで、トラブルを早期に防ぐことができます。
また、動物病院によっては訪問介護サービスやリハビリプランを提供しているところもあるので調べてみるのも一つの方法です。
「家でどうしたらいいか分からない」の不安は、専門家に相談することで具体的な解決策が見つかるでしょう。
まとめ:寝たきりシニア犬介護はがんばりすぎないこと
.png)
シニア犬の介護が長く続くほど、昼夜関係なく「もっとしてあげたい」という思いが強くなるものです。
しかし、愛犬が本当に望んでいるのは、ママさん、パパさんが笑顔でそばにいてくれること。
疲れたときは、少し休みましょう。休むことは“サボり”ではなく、明日の介護を続けるための大切な準備です。

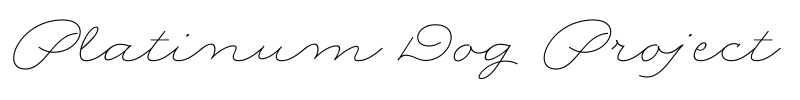


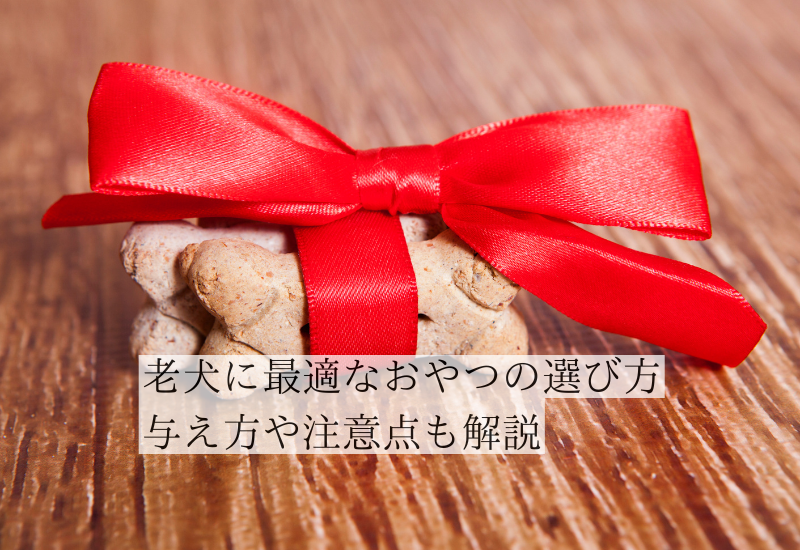


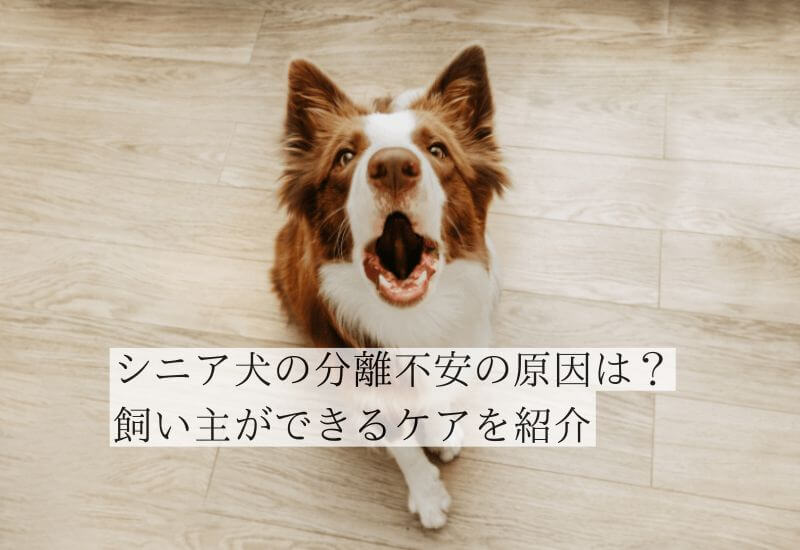








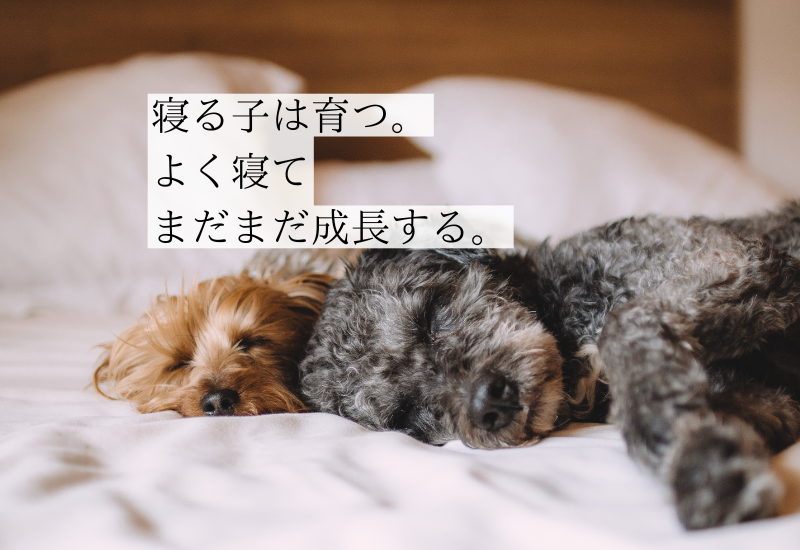
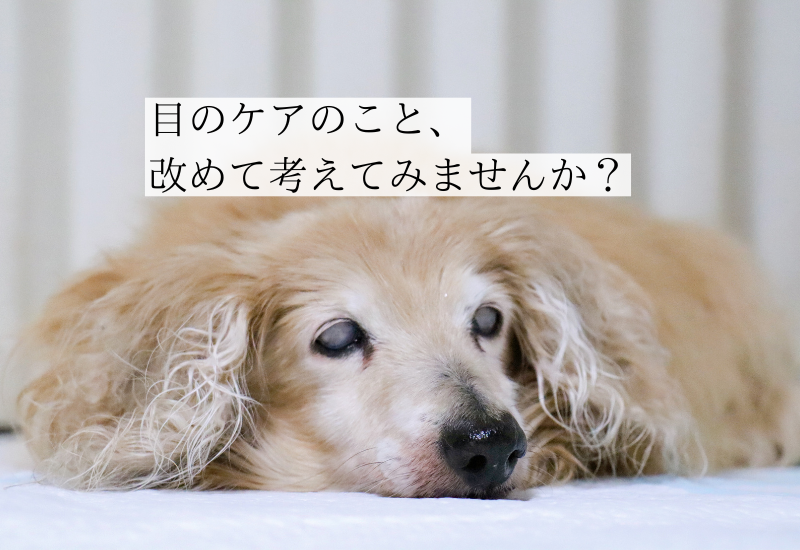




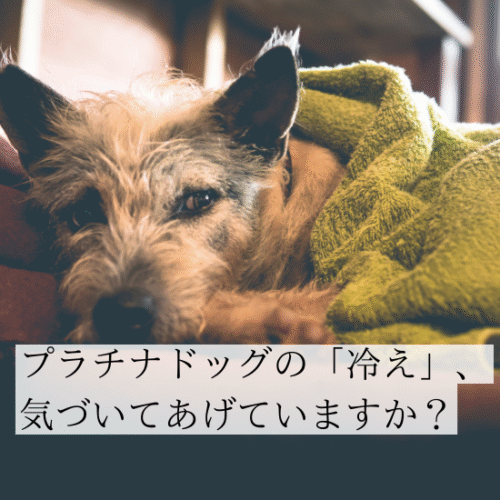



この記事へのコメントはありません。